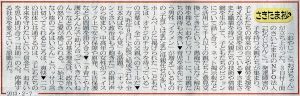アメニティーフォーラムと27本の法律(シンポジウム)参加:滋賀県大津市
障がい福祉フォーラム「アメニティーフォーラム28」2日目 シンポジウムに参加(滋賀県大津市)
2月7日から9日まで滋賀県大津市で開催された、障がい福祉フォーラム「アメニティーフォーラム28」の中で、2日目の14時からは、下記テーマとメンバーのシンポジウムに参加しました。

テーマは「アメニティーフォーラムと27本の法律」
シンポジストは・・・
・高木美智代(公明党アドバイザー)
・山本博司参議院議員(公明党)
・田畑裕明衆議院議員(自民党)
・野村知司(厚労省障害保健福祉部長)
・黒瀬敏文(内閣府政策統括官)
指定討論者として
・佐々木桃子(全国手をつなぐ育成会会長)
・田中伸明(日本視覚障害者団体連合評議員・弁護士)
・尾上浩二(DPI日本会議副議長)
進行役は
・岩上洋一(全国地域で暮らそうネットワーク代表・社会福祉法人じりつ理事長)
本シンポジウムの中で、高木美智代公明党アドバイザーと、山本博司参議院議員のお話しが国会での法制定についての歴史を語りましたので、内容については以下に紹介いたします。

### 高木美智代公明党アドバイザーの講演要旨(アメティーフォーラム28)
高木美智代公明党アドバイザーは、アメティーフォーラム28において、障害福祉に関わる27本の法律制定に関する自身の関わりとその歴史について講演を行った。彼女は、公明党の障害福祉委員長として、障害者自立支援法の改正に尽力した経験を中心に語った。
**1. 障害者自立支援法の改正への取り組み**
2005年に施行された障害者自立支援法は、三障害の一元化や地域生活支援を推進した一方で、利用者負担1割という新たな制度が大きな反発を招いた。高木氏は、公明党の障害福祉委員長に任命された当初、各地で強い反対に直面したが、政権与党として利用者負担の見直しに取り組む決意を固めた。
2007年、自民党との合同プロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、副座長として議論を重ねた。PTでは、個別支援計画のあり方などを見直し、障害者本人や家族の意見を事前に反映させる仕組みを作るなどの改革を進めた。その過程で、8時間に及ぶ会議が続くこともあり、粘り強い交渉の末、利用者負担の軽減を含む改正案がまとめられた。
**2. 政権交代と障害者福祉の法整備**
2007年には政権交代の可能性が高まり、改正法を確実に成立させるための動きが加速した。自民党が主導する形で2度改正案が提出されたものの、成立には至らなかった。そこで、高木氏は、民主党・自民党・公明党の6人で水面下の交渉を重ね、障害者自立支援法の改正、虐待防止法、優先調達推進法の制定など、超党派の協力による法整備を進めた。
2007年12月、参議院の最終本会議において、障害者自立支援法の改正が全会一致で成立した。この改正により、障害福祉の予算は大幅に増額され、国と地方の責任が明確化された。これが、後の福祉政策の基盤となった。
**3. 差別解消法の制定**
高木氏は、障害者の権利擁護の観点から、差別解消法の制定にも尽力した。自民党内では意見が分かれていたが、彼女は衛藤議員との交渉を重ね、法案成立の道筋をつけた。最終的には、超党派の合意を得て、通常国会の閉会間際に全会一致で可決された。この法律は「私たちのことを私たち抜きに決めない」という原則を確立し、日本における障害者政策の大きな前進となった。
**4. 未来への展望**
高木氏は、障害者施策は政争の具とするべきではなく、超党派で取り組むべき課題であると強調した。これまでの成果を踏まえ、ノーマライゼーションの推進や多様性を尊重する共生社会の実現に向けて、今後も支援を続ける決意を述べた。
最後に、高木氏は、障害福祉の法整備に関わったすべての関係者への感謝を述べ、今後も国民の声を政策に反映させるべく努力していくことを誓った。

以下は、山本博司参議院議員がアメニティフォーラム28のセッション「障害者に関わる27本の法律制定」で語られた内容を要約したものです。
山本議員は、自身が2007年に当選して以来、衛藤先生らとともに、障害者施策に関する法律制定に取り組んできた経緯を語っています。当時、野党勢力が多数を占める中で、与党が進める障害者自立支援法の改正、障害者虐待防止法、優先状態の通信法、障害者基本法などの施策に対して、野党として反対や議論が交わされ、なかなか法整備が進まなかった時期があったと振り返ります。
議員在任18年間で、公開選を含めた27本の法案に関わってきた経験から、立法過程における現場の議論や調整の重要性を実感していると述べています。
特に、野党として活動していた2007年~2009年の期間には、障害者施策の推進に向けた基盤づくりのため、反対意見があっても「100点満点でなくても70点でも前に進む」という姿勢で、障害者自立支援法の改正や放課後の発達支援事業、さらには障害者基本法、虐待防止法、優先となる推進法、総合支援法といった関連法案の検討が進められました。
野党内でも、関係者が朝早くから週2回集まるなど、議論と調整を重ね、現実的な一歩を着実に踏み出す努力がなされていたことが伺えます。
また、2010年以降、与野党を超えた流れの中で、障害者基本法がより実効性をもって活用されるようになり、2013年からは障害者差別解消法を皮切りに、議員立法として各種法案が成立していきました。
その中でも特に印象深いと語られたのが「障害者文化芸術の推進の法律」です。2013年2月のアメニティフォーラムで、地域の生活人材ネットワークや教育関係者、そしてアールブリュットのネットワークなど、各方面の意見が集まり、議員や関係者が協力して法改正に向けた活動を始めました。
自民党衛藤先生が中心となり、山本議員自身が事務局長として取り組む中、同年、国会で安倍総理に対して、障害者文化芸術の振興に関する質問を行い、政府内でも関心を高めさせる契機となりました。
その結果、2018年にこの法律が成立するまで、3国会にわたって2年間かけた努力が実を結んだと説明されています。
さらに、現代においては、琵琶湖ホールで行われたユニバーサルツーリズムのイベントのように、万博に向けて障害者団体が国内外(台湾、オーストラリアなど)のネットワークを構築し、文化庁や厚労省の予算支援のもとで、アート、伝統芸能、パフォーマンス、バリアフリー演劇・映画など、多様な分野で障害者が活躍できる環境が整いつつある現状を紹介しています。
こうした動きは、かつてアメニティフォーラムで議員や関係者が結集して法整備に取り組んできた成果であり、障害者の社会参加を大いに促進していると実感しているとのことです。
また、議員になる前にIBMに関わっていた経験を活かし、江戸先生の下で障害者情報コミュニケーションに関する議連を設立。幹事長として、バリアフリー法、電話リレーサービス、情報アクセシビリティに関する法律施策の推進にも寄与したと述べ、地方自治体の町長派の動きや現場の声の大切さも強調しています。
最後に、国土交通大臣としての経験も触れ、交通分野におけるバリアフリー推進の取り組みについても言及しました。例えば、新幹線の車椅子スペースが不足しているという声を受け、迅速に対応するなど、実際の現場で障害者の意見を反映させる施策が進められた点を紹介しています。精神障害者に対する交通割引の制度改正も、JRや民間鉄道で実施され、身体障害や知的障害と同等の対応が取られるようになったとし、こうした具体的な改善事例が、人と人とのつながりの成果であると力説しています。
総じて、山本議員は、野党としての苦労や議員立法による小党派の取り組みを通して、障害者施策に関する27本の法律が成立し、その結果、障害者の自立支援、文化・芸術の振興、情報通信の改善、さらには交通バリアフリーなど、社会全体で障害者の参加と権利拡充が進んでいる現状を力強く伝えています。
そして、こうした法整備の歩みは、当時の関係者の議論や連携、そして現場の具体的な要望に基づくものであり、今後も多様なステークホルダーの協力を得ながら、より良い障害者施策の実現へとつながっていくと確信しているとのことです。