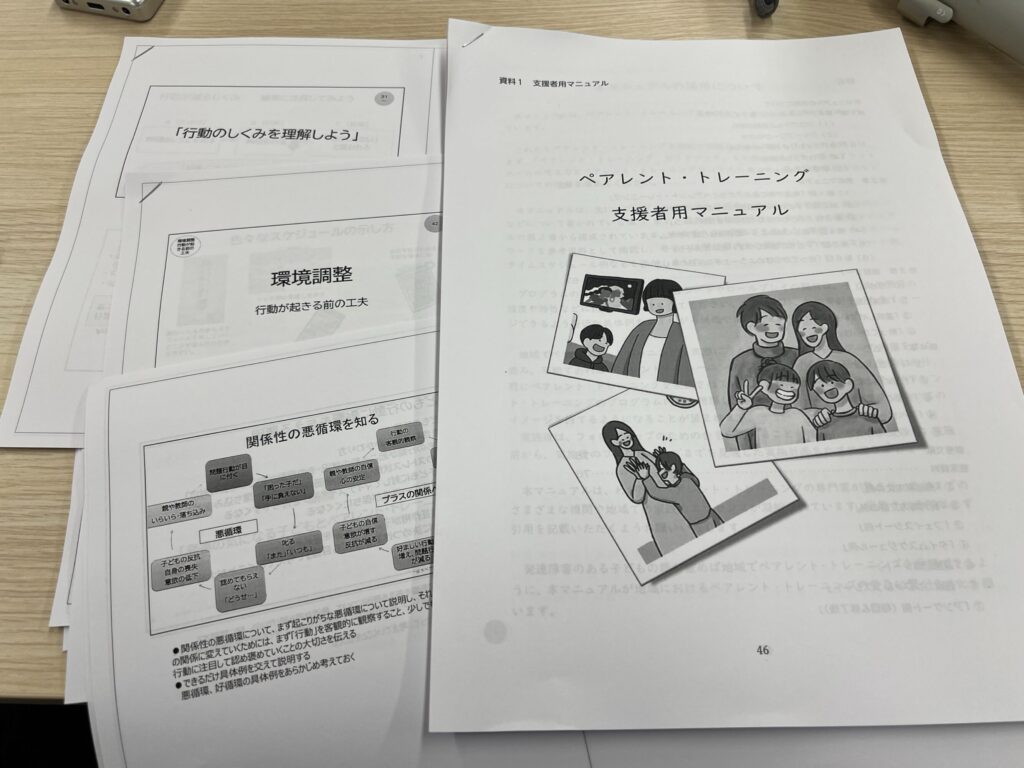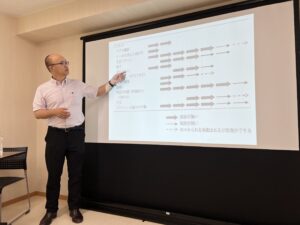ペアレントトレーナー養成セミナーに参加:岩手県北上市
13日は午前中から、夕方まで一日掛けてペアレントトレーナー養成セミナーに参加いたしました。
場所は岩手県北上市。社会福祉法人岩手ひだまり会が主催です。

このセミナーは昨年6月にも開催されており、2回目の参加となります。
前日の、「発達に特性のある児童家族のための勉強会」に引き続き2日連続での勉強会となり、講師は取大学 大学院医学系研究科臨床心理学専攻 臨床心理学講座の井上雅彦教授です。
午前中は講義として、井上教授から、ペアレントメンター制度ついて基礎なお話しがありました。
井上先生は、日本ペアレント・トレーニング協会の会長も務められています。
https://parent-training.jp/
今回、当団体の金子訓隆代表理事は、全体のファシリテーターとして担当いたしました。
参加者は北上地域を中心とした、障害児支援を行う職員の方々約30名です。

ペアレントトレーニングについて歴史から今に至る活動までいかに紹介いたします。
参考資料:ペアレント・トレーニング支援者用マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000799077.pdf
ペアレントトレーニングとは:発達障害のある子どもの保護者への包括的支援
ペアレントトレーニングは、発達障害のある子どもの保護者が子育てに関するスキルを習得し、子どもの問題行動の軽減と発達の促進を目指すプログラムです。その歴史は古く、1950年代には知的障害や重度の自閉症の子どもを持つ家族を対象に始まりました。当初は「親の育て方が悪い」という誤解があったものの、研究の進展により自閉症が生理学的・遺伝的要因に起因することが明らかになり、親が積極的に療育に参加することの重要性が認識されるようになりました。
ペアレントトレーニングの目的と歴史的背景
ペアレントトレーニングは、子どもの発達を促し、問題行動を減らすだけでなく、保護者自身の精神的な健康も守ることを目的としています。このプログラムが始まった背景には、発達障害、特に自閉症に対する過去の誤解があります。
1940年代から50年代にかけて、自閉症の原因は「親の育て方、特に母親の冷たい態度にある」という誤った見解が広く信じられていました。この時代、自閉症の子どもを持つ親は、小児精神科医から「統合失調症」のような精神疾患の一種とされ、子どもはセラピーを受け、親は別の部屋でカウンセリングを受けるという状況でした。親は責められ、深い精神的苦痛を負っていました。
しかし、1950年代以降、自閉症に関する生理学的研究が進み、脳波異常やてんかんとの関連、一卵性双生児研究による遺伝的要因の示唆など、生物学的な側面が明らかになってきました。これにより、「親の育て方が原因ではない」という認識が広まり、自閉症の理解は大きく前進しました。現在のゲノム研究でも、自閉症の特定の原因遺伝子はまだ特定されていませんが、複数の関連遺伝子が関与していることが示唆されており、がんのように単一の遺伝子異常ではないことが分かっています。また、自閉症は複数の生物学的に異なるタイプの人々が含まれているため、その症状や併存疾患が多い理由もそこにあると考えられています。薬物療法についても、特定の薬がすべての人に効果があるわけではないという実態があります。
このような背景から、ペアレントトレーニングは、親を責めるのではなく、親が子どもの療育に積極的に関わることで、早期療育の効果を高め、虐待の予防や親の育児ストレス軽減を目指すものとして発展してきました。トレーニングを通して、親と子どもの関わり方を変え、子どもの問題行動を減らし、発達を促すことが重視されます。メンタルヘルス改善は副次的な効果であり、主要な目的は子どもの発達支援と行動変容にあります。
日本におけるペアレントトレーニングの現状と課題
日本においてペアレントトレーニングは広く導入されていますが、その実施状況にはいくつかの特徴と課題が見られます。
実施状況の概要
日本では、ペアレントトレーニングは多様な場所で実施されています。全国調査(令和2年度)によると、事業所や自治体、医療機関など様々な主体がペアレントトレーニングを提供しています。
- 対象者: 海外のプログラムが診断別に特化しているのに対し、日本では自閉症とADHDなど複数の発達障害を併せ持つ子どもを持つ保護者が、診断の有無にかかわらず同じグループでトレーニングを受けることが一般的です。これは、実際の現場では診断名が明確でないケースや、複数の診断を持つ子どもが多いという実態を反映しています。未就学児から中学生前半まで幅広い年齢の子どもが対象となることも多く、本来であれば中学生向けのプログラムは未就学児向けとは大きく異なるはずですが、現状では同じプログラムが用いられることもあります。
- 実施回数と形態: グループ形式で実施されることが多く、1グループあたり4~7人の保護者が参加し、5~6回程度の連続講座として提供されるのが主流です。海外では自閉症の場合、個別訪問支援が中心となることもありますが、日本ではグループ形式が多いです。
- 実施者: 心理士が最も多いですが、保育士、作業療法士、言語聴覚士など多職種の専門家が担当しています。プログラムの実施には、3~5年程度の臨床経験を持つ中堅レベルのスタッフが望ましいとされています。新卒のスタッフがすぐに担当することは難しいと考えられています。
- 加算制度: 児童発達支援や放課後等デイサービスでは「家族支援加算」が設けられており、これらを活用することで事業所の収益につながる可能性があります。遠隔での実施や集団での実施も可能とされています。
日本における課題と「ペアレントトレーニング」問題
日本でペアレントトレーニングを普及させる上での大きな課題は、その実施回数にあります。エビデンスに基づいた先行研究では、プログラムの効果を最大化するために10回以上のセッションが推奨されています。しかし、日本の現場では、保護者の参加負担や事業所のキャパシティの制約から、5~6回程度の「短縮版」が主流となっています。
この「短縮版」の普及は、本来のプログラム内容を十分に伝えきれない「なんちゃってペアレントトレーニング」になってしまう懸念があります。研究者は理想的なプログラム(例えば「月に行くような最高のプログラム」)を開発したがりますが、現場の実態(「5~6回程度のプログラムしか実施できない」)に即した効果的なプログラムを開発し、普及させることが求められています。これは、まるでF1カーと一般車のような違いです。研究で示されるF1カーのような最先端のプログラムを、誰でも安全に運転できる一般車に落とし込み、現場で実践できる形にすることが重要です。
また、異なる流派の専門家がそれぞれ独自のペアレントトレーニングを実施し、時に意見の対立が見られることもありました。
「基本プラットフォーム」の策定と質の向上への取り組み
このような課題を解決するため、日本の研究者や実践者が集まり、流派を超えて共通の基本要素を抽出した「基本プラットフォーム」が策定されました。これは、ペアレントトレーニングの質を保証するためのもので、「コアエレメント」と呼ばれる必須の内容(例:行動の観察、褒め方、望ましくない行動への対処法など)が示されています。これは、幕の内弁当に必ず入れるべき「おかず」のようなもので、この6つの要素が盛り込まれていれば、どのような形式や回数であっても「ペアレントトレーニング」として認められるという考え方です。
さらに、ペアレントトレーニング研究会(一般社団法人)が設立され、研究者と実践者が協力して日本のペアレントトレーニングの質を高めるための活動を行っています。
ペアレントトレーニングの効果と対象者の理解
ペアレントトレーニングは、子どもの行動改善だけでなく、保護者の育児ストレスや抑うつ状態の軽減にも効果があることが示されています。筆者の研究グループが鳥取県で長年にわたって実施したペアレントトレーニングのデータでは、参加した保護者の子育てストレスや抑うつが改善傾向にあることが示されました。
グレーゾーンの子どもと家族への支援
発達障害の診断は、医師の主観も大きく影響し、同じ症状でも病院によって「グレーゾーン」と判断されることがあります。また、診断名がついていても、他の発達障害の症状を併せ持っていることも多く、研究によっては自閉症と診断された子どもの半分以上が他の発達障害の症状を併存しているという報告もあります。
例えば、自閉症と発達性協調運動障害(DCD:不器用さ)を併発しているケースは少なくありません。診断名にとらわれず、目の前の子どもがどのような困難を抱えているかを正確に把握し、適切な支援を提供することが重要です。
特に、「診断ライン」という概念は重要です。自閉症の特性は連続性があり、全く特性がない人は逆にいません。こだわりなど、誰もが何かしらの特性を持っています。特性が強いほど診断がつきやすいですが、診断ラインぎりぎりの人や、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる子どもたちが多数存在します。これらの子どもたちは、環境が良ければ特性が目立たなくなることもありますが、環境が悪化すると症状が顕著になることがあります。学校の通常学級には、診断を受けていないものの、診断を受けている子どもよりも強い特性を持つ子どもも少なくありません。発達障害者支援法では、発達障害の「疑いのある人」も支援の対象とされており、診断の有無にかかわらず、困難を抱える子どもと家族への支援が求められています。
ペアレントトレーニング実施上の工夫と留意点
ペアレントトレーニングを効果的かつ安全に実施するためには、様々な工夫と留意点が必要です。
参加者の募集と評価
- 募集方法: 既存の教室やデイサービス利用者への呼びかけが最も効果的です。他の事業所と提携して、家族支援加算を活用することも考えられます。大学での公開講座形式のように、参加者の情報が事前に少ない場合は、より丁寧な対応が求められます。
- 事前・事後評価: プログラムの実施前後に、保護者の育児ストレスや抑うつ状態を測るための簡単なアセスメントを行うことが推奨されます。これは、保護者の状態を把握し、適切な配慮を行うため、またプログラムの効果を測定するためにも重要です。厚生労働省の研究で作成された尺度など、既存のツールを活用することも可能です。
- インフォームドコンセント: アセスメントを行う際には、その目的と内容について十分に説明し、保護者の同意を得る(インフォームドコンセント)ことが不可欠です。保護者の中には、精神科や心療内科に通院している方、過去にトラウマ体験を持つ方もいるため、デリケートな情報に配慮し、信頼関係を構築した上で進める必要があります。
プログラムの運営
- 守秘義務の徹底: グループワークでは個人的な内容が共有されるため、プログラム開始前に守秘義務について徹底的に説明し、参加者が安心して話せる環境を整えることが最も重要です。「部屋を出たらすべてを忘れる」という共通認識を持つことが求められます。特に地方では、地域の狭い人間関係の中で情報が漏洩することによるトラブルを防ぐため、細心の注意が必要です。
- 安全な場づくり: 参加者の中には、人と話すのが苦手な人や、過去の経験から傷つきやすい人もいます。スタッフは、常に個々の参加者に配慮し、発言しづらい人にはサポートスタッフが寄り添うなど、安心できる雰囲気作りを心がける必要があります。
- スモールステップと「褒める」ことの重要性: 最初からすべてを完璧にやろうとせず、段階的に進めることが有効です。特に「褒める」ことはペアレントトレーニングの中心的な要素であり、最も重要なスキルの一つです。保護者が子どもの良い行動に注目し、具体的に褒める練習をすることで、親子の肯定的な関係性を築くことができます。
- 「他と比べない」姿勢: グループワークでは、他の親子の成功体験を聞いて、自分の子どもと比較し、劣等感を抱いてしまうことがあります。支援者は、参加者が「自分のお子さんの、プログラム参加前と比べての変化」に焦点を当てるよう促し、他者との比較ではなく、自己の成長に目を向けさせるように配慮する必要があります。
- 宿題の重要性: 学んだ知識を実践に活かすため、宿題は不可欠です。しかし、宿題に取り組むのが難しい保護者もいるため、ドロップアウトを防ぐためにも、柔軟な対応と継続的なサポートが求められます。
- 困難なケースへの対応: プログラム中に、精神的に不安定な保護者や、グループの雰囲気を損なうような発言をする保護者が出ることもあります。このような場合、支援者は冷静かつ適切に対処し、必要に応じて個別カウンセリングなど、次の支援につなげることが重要です。ペアレントトレーニングだけでは解決できない問題もあることを認識し、専門機関への紹介も視野に入れるべきです。
- ペアレントメンターの活用: ペアレントメンターとは、子育て経験が豊富で研修を受けた先輩保護者のことです。彼らがプログラムに参加することで、参加する保護者は共感や具体的なアドバイスを得やすくなり、安心してプログラムに取り組むことができます。メンターは、各都道府県の発達障害者支援センターなどで養成されており、地域のネットワークを通じて協力を求めることができます。
実施者の育成とスーパービジョン
ペアレントトレーニングは、単に座学で知識を伝えるだけでなく、参加者の状況に合わせて柔軟に対応するスキルが求められます。そのため、実施者の継続的なスキルアップが不可欠です。
- スーパービジョン: 新任の実施者や経験の浅い実施者に対しては、経験豊富な専門家によるスーパービジョンが非常に有効です。これにより、実践の中で生じる疑問や困難を解消し、支援技術の向上を図ることができます。鳥取県では、心の診療拠点病院のスタッフが地域のペアレントトレーニングのスーパービジョンを行っている事例もあります。
- 段階的な展開: 最初からフルバージョンのプログラムを実施するのではなく、「褒める教室」だけを独立して実施するなど、段階的にプログラム内容を広げていくことも有効です。これにより、実施者も経験を積みながらスキルを向上させることができます。
今後の展望
ペアレントトレーニングは、現在のシステムでは収益性が高い事業とは言えませんが、スタッフと保護者間の信頼関係を深め、スタッフの専門性を高める上で非常に価値のある支援です。保護者との良好な関係は、子どもの支援にも良い影響を与えます。
近年では、インターネットを通じたペアレントトレーニングも研究されており、対面とほぼ同等の効果が報告されています。オンラインでの実施は、地理的な制約を受けずに支援を提供できるという大きなメリットがあります。岩手県のような広範囲な地域では、沿岸部と内陸部、南北のアクセスに課題があるため、オンラインでのペアレントトレーニングは有効な選択肢となり得るでしょう。
また、ペアレントトレーニングは、就学前の小さい子どもを対象としたものが中心ですが、思春期以降の「思春期・青年期のペアレントトレーニング」も開発が進んでいます。思春期の子どもへの褒め方や、反抗期への対応など、小さい子どもとは異なる内容が必要となるため、今後、年齢層に合わせたプログラムの充実が期待されます。
ペアレントトレーニングは、単に知識を与えるだけでなく、保護者自身が実践を通して子育てスキルを向上させ、子どもとのより良い関係を築くための総合的なプログラムです。その質を高め、より多くの保護者がアクセスできるよう、今後も継続的な研究と地域での連携が重要となるでしょう。