令和6年度の障害福祉サービスに関わる補正予算概要
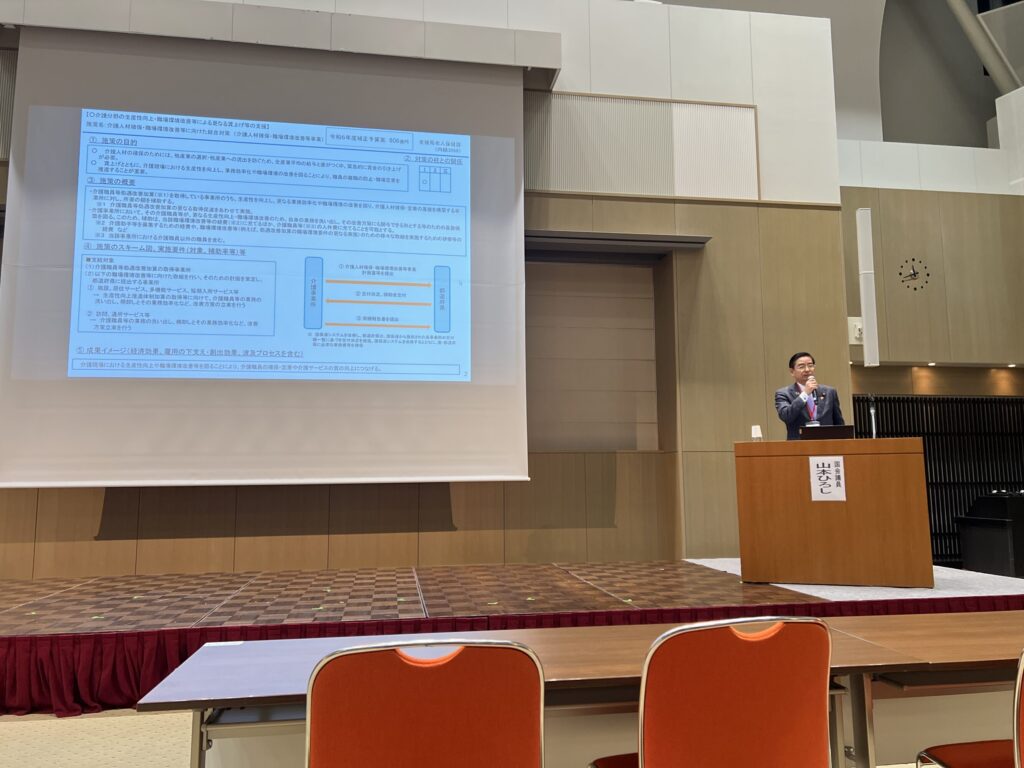
1月12日、あいサポートとっとりフォーラムにて基調講演をされた、山本博司参議院議員の講演内容に基づき、令和6年度の障害福祉サービスに関わる補正予算の概要についてまとめました。
なお、福祉サービスに従事する団体については3月頃を目処に自治体より、事業所が従業員の賃金改善や職場環境改善に関する通達があるかと思います。
なお、こちらの文責は、特定非営利活動法人輝HIKARIにあります。
もし修正や間違い等ありましたらご連絡ください。
以下に、山本博司参議院議員が「あいサポートとっとりフォーラム25」(令和7年1月10日~12日・鳥取県米子市)にて行った特別講演を中心に、令和6年度の障害福祉に関する補正予算のポイントと、フォーラム全体の総括を参議院議員の立場から要約いたします(約5000字程度)。
1.はじめに
本フォーラムは、障がいのある当事者や家族、専門家、行政関係者などが一堂に会し、障害福祉分野における最新の課題や取組状況を共有・議論する場として3日間にわたり開催された。山本議員は同フォーラムに2日間参加し、最後の特別講演で総括と今後の国の施策・予算措置などについて言及。特に「令和6年度障害福祉に関する補正予算の話」と、フォーラムで扱われた「今後の日本の障害福祉行政の方向性(親なきあと、地域生活支援拠点事業、重層的支援事業など)」が重要なポイントとして示された。
2.フォーラム全体の概要と主なトピック
(1)開催概要
- 開催日:1月10日~12日
- 開催地:鳥取県米子市
- 全体テーマ:「あいサポートとっとりフォーラム25」
- 内容:障害福祉にかかわる分科会・講演・シンポジウム・国際的な視点を取り入れたセッションなど多岐にわたるプログラムを実施。
山本議員は、冒頭あいさつの中で「実行委員会が真摯に現場ニーズを受け止め、直近の課題を深めるテーマ設定を行っている」と述べ、フォーラムの意義の大きさを強調。また、行政トップ(厚生労働省の事務次官や障害福祉部長、子ども家庭庁審議官等)や海外からの登壇者(ルワンダの教育支援に携わる方)を招いて意見交換できる機会の重要性にも触れた。
(2)主なテーマと講演
- 精神障害・メンタルヘルスの早期支援
- 我が国では3障害(身体・知的・精神)のうち精神障害の方が年々増加し、年間の受診者数は600万人を超える。早期治療・支援体制の整備が急務であることが議論された。
- 国際的視点(ルワンダの事例)
- 1994年のジェノサイドの歴史を経たルワンダでの教育や女性の就労支援の取組紹介。日本人専門家やJICA関係者の活動状況も紹介され、「世界市民としての支援の在り方」について考える機会となった。
- 各種分科会
- てんかん
- 国内に約100万人いると言われるてんかん。当事者の支援環境と偏見除去に向けた啓発活動が必要。てんかん地域診療連携体制整備事業予算の拡充(令和6年度予算で倍増)なども進められている。
- 就労支援・農福連携
- 農業と福祉の連携(農福連携)の全国的拡充。担い手不足の農業分野で障害のある人の就労機会が拡大する事例が増え、厚労省・農水省ともに予算を拡充している。
- 地域共生社会の実現(地域生活支援拠点事業や重層的支援事業)
- 親なきあとや障害の重度化、高齢化に伴う地域での支え合い。
- 重層的支援事業では、ひきこもりやヤングケアラーといった「障害」とは異なる領域にも相談や支援を統合的に届けることが重要となっている。
3.令和6年度 障害福祉に関する補正予算の概要
山本議員は、昨年末に成立した補正予算(総額13兆9,433億円)のなかでも、特に物価高騰対策と障害福祉・介護分野における人材確保や処遇改善に言及した。以下は山本議員の説明をもとにまとめたポイントである(※講演では「介護」「障害福祉」「子ども家庭庁関連」など合わせて触れられている)。
(1)全体のねらい
- 物価高騰対策
- 日本の成長促進投資
- 安心安全の確保(災害対応含む)
障害福祉・介護分野では、民間企業の賃上げが進む中、報酬改定による賃金引き上げが必ずしも追いつかない。そこで、補正予算において賃金の上乗せや人材確保・定着のための支援を強化する。
(2)障害福祉分野
a. 総額と主な内訳
- 障害福祉全体:874億円
- 職員処遇改善:284億円
- (うち障害児への対応は子ども家庭庁の所管分を合わせると343億円)
- ICT・テクノロジー導入支援:16億円
- 就労施設の生産活動支援:9億円
- 施設整備費:132億円
b. 職員処遇改善の仕組み
- 事業所が計画書を都道府県へ提出 → 都道府県が交付金(国の補助)を支給決定 → 事業所が従業員の賃金改善や職場環境改善に充当。
- 1人あたり月9千円×6ヶ月(計約5万4千円相当)を基準とし、追加的な人件費などに使える。
- 実施スケジュールは厚労省が1月頃に各都道府県へ通知し、事業所が年度末あたりで申請。支給はおおむね6月の賞与時期を目途に想定。
c. 重点支援地方交付金(1兆1,000億円)
- 物価高騰等により食費や燃料費等が上がっている施設・事業所に対し、地方自治体の判断で支援が可能な交付金。
- 障害福祉だけでなく幅広い分野で活用されうるが、自治体が独自の支援策を講じる際の財源となる。
d. 施設整備費(132億円)
- 本予算(約70億円)に加え、補正予算で増額。
- グループホーム新設や既存施設の老朽化対策、災害対応などの設備改修費用を支援。
(3)介護分野(参考)
- 介護分野 全体:1,103億円
- 人材確保の処遇改善:806億円
- ICT導入支援:200億円
- 訪問介護のサービス維持支援:90億円
- 処遇改善は障害福祉と同様、1人あたり月9千円程度の緊急的な賃上げを想定。
4.フォーラムで議論された施策・今後の展望
(1)てんかんへの支援
- てんかんは国内に約100万人の当事者がいると推定。いまだ誤解や偏見が根強い。
- 「てんかん地域診療連携体制整備事業」
- 全国に30か所ある拠点病院を中心に、地域啓発セミナーや相談体制を整備。令和6年度より予算が倍増する方向。
- 教育現場などでの対応や、医療・福祉連携のさらなる推進が課題。山本議員自身も娘さんが知的障害を伴うてんかん当事者であり、「国として支援を強化する」と強調。
(2)就労支援・農福連携
- 米子市や岡山県の事例で、農業と障害福祉を組み合わせた事業の成功事例が紹介。
- 山本議員が国会で農福連携を初めて提起した際、農水省・厚労省間で協議が進み、農水省の予算が大幅に拡充。農業基本法にも農福連携が明記されるようになった。
- 高齢化が進む農業分野での担い手確保と、障害のある人が地域で働ける場の創出が「ウィンウィンの関係」を築くとの評価。
(3)地域生活支援拠点事業・重層的支援事業
- 地域生活支援拠点事業
- 親なきあとや緊急ショートステイの確保、専門的ケアや相談のハブ機能を担う拠点を地域単位で整備する。令和4年の障害者総合支援法改正で、市町村に「努力義務」として位置づけられた。
- 埼玉県深谷市など広域的に拠点を設置し、障害特性に応じた支援を行う先進事例が紹介。
- 重層的支援事業
- ひきこもり、8050問題、ヤングケアラーなど、「障害」の枠組みだけに収まらない複合的課題をもつ人々に包括的に支援する仕組み。
- 山本議員が国会質問(2007年)で「ひきこもり」に言及した当時はまだ厚労省の実態把握が進んでいなかったが、現在は生活困窮者自立支援や重層的支援事業へとつながりつつある。
5.フォーラム全体の総括と今後の展望
(1)障害福祉施策の強化と予算拡充
今回の補正予算で大きく取り上げられたのは、人材確保のための処遇改善と施設整備の充実である。民間企業の賃上げに遅れをとりがちな介護・障害福祉現場を支えるため、国として緊急的に賃金上乗せを図る方向が示されたことは評価できる。一方で、補正予算だけではなく本予算での恒久的な報酬改善が必要との声も現場から強い。今後も引き続き、処遇改善や重層的支援の制度化が課題となる。
(2)地域共生社会に向けて
- 地域生活支援拠点事業
- 重度障害者や行動障害のある人、医療的ケアが必要な人を含め、安心して地域で暮らせる拠点機能が鍵を握る。
- 各自治体・関係機関・家族会・民間事業者などが連携し、地域全体で取り組む姿勢が求められる。
- 重層的支援事業
- 障害に限定されず、「生きづらさ」を抱える多様な人々を包括的に支援する仕組み。
- ひきこもり、ヤングケアラーなど政策領域を越えた連携が必要。行政内の縦割りを解消し、相談窓口の一本化やワンストップサービスをどう構築していくかが焦点。
(3)国際的視点の取り込み
- ルワンダの事例が示すように、戦禍や虐殺を経た社会でも教育や女性就労支援などを通じて目覚ましい発展がある。日本の支援活動(JICAやNPOによるミシン技術指導等)との協働事例も参考になる。
- “世界市民”として、特に新興国や紛争地域など、障害を抱える人への支援ノウハウを共有・拡大することは、日本国内の福祉行政にも新たな視点をもたらす。
(4)今後の政治的役割
- 山本議員は、障害を持つお子さんの父親という当事者的な立場で、引き続き「政治や議会が果たせる支援」を追求していく姿勢を示した。
- ご自身は本年7月で参議院議員を退任予定だが、引き続き国政・自治体・現場を結びつける役割を担う意向を強調。
- 議員・行政・家族・民間がそれぞれの立場で連携することで、政策を現場に届かせる重要性が再確認された。
6.まとめ
「あいサポートとっとりフォーラム25号」での特別講演を通じ、山本博司参議院議員が強調したのは以下の点である。
- 障害福祉と介護分野の処遇改善・人材確保
- 令和6年度の補正予算では、物価高騰や民間企業の賃上げに対応するかたちで、介護・障害福祉現場への交付金が大幅に拡充。事業所における給与上乗せ・職場環境改善に活用される予定。
- さらに施設整備費やICT活用支援金も用意され、地域での多様な取り組みを支える。
- 農福連携・てんかん支援などの各分野の進展
- 農業基本法への農福連携明記、てんかん地域診療連携体制整備事業の予算拡充など、分野横断型の支援体制が強化されている。
- 地域生活支援拠点事業・重層的支援事業の全国展開
- 親なきあとの暮らしや緊急時対応を見据え、地域が機能を有機的に連携させる重要性。
- 障害の種別を超えた重層的支援事業が今後、広がりを見せることで、ひきこもりやヤングケアラー等、多岐にわたる支援ニーズに応える。
- 国際的視点の導入
- ルワンダの事例やJICA・NPOの活動等から学び、国内外での障害者支援を強化すべきと再認識。
このように、フォーラム全体を通して「現場の視点から行政・政治を動かす」「全国で共有できる知見を持ち寄る」ことの重要性が改めて示された。障害福祉を取り巻く課題は多岐にわたり、今後も予算措置のみならず、地域拠点の設置や多職種連携・関係機関の連携強化が必須となる。
山本議員は最後に「同じ障害のある子の親として、また政治家として、退任後も引き続き障害福祉施策のさらなる充実に取り組む」と述べ、フォーラム参加者への感謝とともに講演を締めくくった。
以上が、令和6年度の障害福祉に関する補正予算のポイントと、あいサポートとっとりフォーラム25号における山本博司参議院議員の講演・総括の主な内容である。障害福祉施策の今後の方向性としては、「処遇改善の継続」「地域生活支援拠点事業・重層的支援事業の拡充」「多様な当事者のニーズを拾い上げる総合的な仕組み作り」「国際的視点を踏まえた支援」が鍵になると考えられる。


