令和8年度 障害保健福祉部予算概算要求の概要について懇談:永田町
5日午後、永田町の原田大二郎参議院議員事務所にて、厚生労働省の野村知司障害保健福祉部長から令和8年度の障害保健福祉部予算概算要求の概要について伺いました。
この懇談には、原田大二郎参議院議員、山本博司氏(前参議院議員)、小野寺徳子氏(元厚生労働省障害者雇用対策課長・元福岡労働局長)が参加され、輝HIKARIの金子訓隆代表理事も同席させて頂きました。
また厚生労働省からは企画課長、経理課長もご同席されました。

約1時間に渉り、来年度の予算概算要求について参加者で協議しました。
第1部:令和8年度障害福祉予算の全体像
◆参考URL
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/dl/gaiyo-11-1.pdf
- 予算規模の拡大と構造
野村部長の説明によると、令和8年度の障害保健福祉部が要求する予算案は、令和7年度の2兆2,000億円強から約1,000億円増(5.8%増)となる2兆3,000億円規模に達する見込みである。この予算の根幹をなし、全体の7割から8割を占めるのが、障害福祉サービスの提供に要する義務的経費である。
この義務的経費は、ホームヘルプや施設サービス、グループホームの運営費などに充当され、いわば介護保険制度における介護報酬と同様の位置づけを持つ。国の負担が概ね2分の1、地方自治体が残り2分の1を担う構造となっている。この部分だけで、令和7年度の1.7兆円から令和8年度には1.8兆円へと、1,000億円強の伸びが見込まれている。さらに、こども家庭庁に移管された障害児支援の予算(約5,000億円)も同様に5%程度の伸びを示しており、これらを合算した障害福祉サービス全体の給付費は2兆円を大きく超える規模に成長している。 - サービス費増大の背景
この予算規模の拡大、いわゆる「自然増」の背景には、二つの大きな要因が存在する。
第一に、利用者数の増加である。成人(18歳以上)の分野では、特に40代、50代で気分の落ち込みなどから支援を必要とする精神障害者の利用が顕著に増加している。また、児童の分野では、就学前・就学後を問わず、言葉の遅れなどに対応する発達支援や放課後等デイサービスの利用者が増えており、その多くが発達障害を理由としている。
第二に、一人当たりのサービス単価の上昇である。これは、職員の給与水準を引き上げるための処遇改善などが報酬単価に反映されているためだ。
このように、「利用者数(横軸の拡大)」と「一人当たり単価(縦軸の伸長)」が掛け合わされることで、障害福祉サービス費は毎年着実に増加を続けており、この財源をいかに安定的に確保するかが、予算編成における最重要課題となっている。 - 義務的経費以外の主要な取り組み
予算全体に占める割合は小さいものの、障害者の生活を多角的に支えるための重要な施策も盛り込まれている。
•生産性の向上と質の確保: 介護テクノロジー(入浴用リフトなど)の導入支援や、間接業務の効率化を推進する。これにより、職員が利用者に直接向き合うケアの時間を創出することを目指す。また、処遇改善加算の取得に伴う煩雑な事務作業をサポートするなど、小規模事業所への支援も含まれる。
•地域生活支援事業の拡充: 外出の援助、日中の交流活動の支援、手話通訳者の派遣など、市区町村が地域の実情に応じて弾力的に展開する事業を支援する。要求額は502億円から530億円への増額を目指しているが、自治体の事業規模が拡大する中で、国の補助率は3割強に留まっており、現場からは大幅な拡充を求める声が根強い。しかし、この経費は裁量経費であるため、財務省との折衝は毎年厳しいものとなっている。
•施設整備費の確保: グループホームの新設や、昭和末期から平成初期に建設され老朽化が進む施設の改築・耐震化などを支援する。当初予算で50億円規模を確保しつつ、国土強靱化計画などの名目で補正予算による上積みを重ね、年間で100億円前後の事業規模を確保するのが近年のパターンとなっている。利用者の増加と施設の老朽化更新の需要は根強く、安定的な予算確保が不可欠である。
その他にも、読書バリアフリー法に基づく点字図書環境の整備、悪質な事業者に対する監査体制の強化、精神障害者が地域で孤立しないための包括的なケアシステムの構築、アルコール・薬物・ギャンブル等への依存症対策、強度行動障害を持つ人への専門的な支援を行える人材の育成など、きめ細かな施策が要求に盛り込まれている。
第2部:職員の処遇改善と職場環境
- 予算編成における最大の宿題
障害福祉分野が直面する最大の課題は、物価高騰への対応と、現場を支える職員の処遇改善である。この二つは、令和8年度予算編成過程における「宿題」として、極めて重要な位置を占めている。
処遇改善の財源は、前述の障害福祉サービス費の報酬単価に上乗せされる形で確保される。具体的には、事業所が特定の要件を満たすことで算定できる「処遇改善加算」という仕組みが中心となっている。この方式は、確実に職員の給与に還元されることを担保する上で有効である。もし基本報酬を一律に引き上げた場合、営利目的の強い一部の事業者が、増額分を職員の給与に回さず、企業の利益として内部留保してしまう懸念があるためだ。
一方で、この加算方式は、申請のための書類作成や給与規定の改定など、事業所、特に事務職員が少ない小規模事業所にとっては大きな負担となっているという現実もある。現場からは「手続きを簡素化してほしい」「加算ではなく基本報酬を引き上げてほしい」という切実な声が絶えない。 - 民間賃金との格差と今後の課題
令和6年度の報酬改定では、令和6年・7年度分の処遇改善が織り込まれているが、令和8年度以降の改善をどう進めるかは、今回の予算編成過程で結論を出さなければならない。
大きな課題は、近年5%を超える高い伸びを示している民間企業の賃上げとの乖離である。同じ率で賃上げを行っても、もともとの賃金水準に差があれば、その「額」の差は開く一方である。この構造的な問題に対し、野村部長は「率だけでなく、額にも目配りする必要がある」と言及し、福祉分野の賃金水準を抜本的に引き上げることの重要性を示唆した。
また、賃上げの実施時期も焦点となる。診療報酬改定が6月施行であることに合わせ、福祉分野の報酬改定も6月実施となった場合、4月・5月分の空白期間をどう埋めるかという問題が生じる。前年度は、この「つなぎ」として補正予算で対応した経緯があり、今回も秋の経済対策やそれに伴う補正予算の動向が、足元の賃上げと来年度の制度設計の両方に大きく影響することになる。 - 職場環境の改善と生産性向上
処遇改善と同時に、職員が働き続けられる職場環境の整備も不可欠である。福祉人材の離職理由を調査すると、給与の低さ以上に「職場の人間関係」や「風土に馴染めない」といった理由が上位に来るというデータもある。
この点について、予算案では介護テクノロジーの導入支援やICT化による事務負担の軽減などが盛り込まれている。これらは、職員の身体的・精神的負担を軽くし、それによって生まれた時間や心の余裕を、利用者とのより丁寧なコミュニケーションに充てることを目的としている。介護分野に比べて障害分野ではテクノロジー導入が遅れているが、成功事例の「見える化」などを通じて、現場の意識改革を促し、普及を進めていく方針だ。
第3部:深刻化する人手不足と外国人材の活用(本件については、輝HIKARIの金子訓隆代表理事より議題提案)
- 慢性的な人材不足と現場の危機感
障害福祉の現場は、慢性的な人手不足に喘いでおり、新卒採用がゼロになる事業所も出るなど、状況は年々深刻化している。この課題を克服するため、外国人材の活用に期待が寄せられている。
現在、障害福祉分野に特化した外国人材受け入れのための予算はないものの、介護分野と同様の制度的枠組みの中で受け入れは進められている。かつては入所・通所施設に限定されていたが、現在では訪問系のサービスでも外国人材の就労が認められるなど、門戸は広がりつつある。 - 障害分野における外国人材活用の課題
しかし、介護分野に比べて障害分野では外国人材の活用が進んでいないのが実情だ。現場からは、その理由としてコミュニケーションの難しさが挙げられる。
身体的な介助が中心であれば言語の壁は比較的乗り越えやすいが、障害福祉の現場では、利用者との対話を通じた精神的なケアが極めて重要となる。特に、知的障害や自閉傾向のある人、強度行動障害のある人への支援には、相手の特性を深く理解し、臨機応変な対応が求められるため、高い言語能力と専門的な知識・スキルが不可欠となる。「夜勤を一人で任せられるか」といった具体的な場面を想定すると、現場が慎重になるのは無理もない。 - 新たな可能性と国際貢献
一方で、外国人材の活用には新たな可能性も秘められている。例えば、両親が国際結婚で、日本語が不得手なために支援が必要となっている子どもに対し、その子の母国語を話せる外国人支援者が関わることで、コミュニケーションが劇的に改善するケースも報告されている。これは、多様化するニーズに対応する上で大きな強みとなり得る。
また、日本で高度な福祉のスキルや事業所のマネジメント手法を学んだ外国人材が、その知識を母国に持ち帰ることは、ASEAN諸国をはじめとする各国の福祉水準の向上に貢献する国際協力の側面も持つ。
人材不足という喫緊の課題に対応するためには、現場の不安を払拭するためのサポート体制や研修を充実させながら、外国人材の受け入れをより一層推進していくことが不可欠である。
第4部:障がい者の就労支援の現在地と展望(本件については、全国各地の視察から各団体の意見として集約したものを、輝HIKARIの金子訓隆代表理事より議題提案)
- 重度障害者の就労を支える「雇用と福祉の連携」
障害のある人が地域で自立した生活を送る上で、「働く」ことは極めて重要なテーマである。特に、障害が重いために就労が困難とされてきた人たちへの支援が強化されている。
従来、労働時間中に公的な福祉サービス(ヘルパー利用など)を使うことは原則として認められていなかった。しかし、令和2年度から、福祉の補助金と障害者雇用制度の助成金を組み合わせ、重度訪問介護の対象となるような重度の障害者が、職場内でヘルパーの支援を受けながら働けるようにする「雇用と福祉の連携」事業が始まっている。この事業の利用者は年々増加しており、来年度予算でも増額が要求されている。 - 期待と混乱の中にいる「就労選択支援」
令和7年度から本格的に始まる「就労選択支援」は、就労支援分野における大きな変化の一つだが、現場では期待と同時に混乱も生じている。
この制度の目的は、特別支援学校の卒業時や、就労継続支援B型事業所などを利用している人が、より本人の希望や適性に合った働き方を見つけられるよう、第三者的な視点から就労アセスメント(評価・分析)を行うことにある。これにより、利用者が一つの事業所に漫然と留まり続けるのではなく、一般就労への移行など、次のステップに進むことを後押しする狙いがある。
しかし現場からは、「就労移行支援や就労定着支援といった既存のサービスとの役割分担が分かりにくい」「地域の相談支援専門員の仕事と何が違うのか」といった声が多数上がっている。野村部長は、この制度が本人の意思決定を支える重要な機能を持つと同時に、一部の事業所による利用者の「抱え込み」を防ぐ牽制機能も期待できると説明する。今後、制度の趣旨を現場に丁寧に周知していくことが成功の鍵となる。 - 就労支援制度の未来
現在の障害者就労支援は、A型、B型、移行支援、定着支援、選択支援など、制度が細分化・複雑化しており、「福祉の枠組みに偏りすぎている」との指摘もある。今後は、福祉と雇用(経済)の垣根を越え、より一体的で分かりやすい支援体系を構築していくことが、長期的な課題となるだろう。


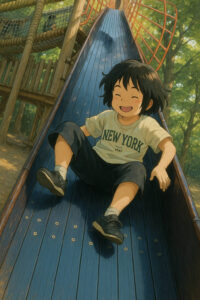

“令和8年度 障害保健福祉部予算概算要求の概要について懇談:永田町” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。