日本発達系作業療法学会 第13回学術大会に参加 Vol.2
日本発達系作業療法学会 第13回学術大会に参加 Vol.2
3月15日と16日、東京保健医療専門職大学講堂で、日本発達系作業療法学会 第13回学術大会が開催されました。
日本発達系作業療法学会 第13回学術大会
https://h-ot13.secand.net/index.html
16日の2日目、うめだ・あけぼの学園 学園長 酒井康年氏(作業療法学会常務理事)のご講演「こどもの笑顔とつながりを作る仕組みと発達系作業療法とのつながり」というテーマでお話しされました。
作業療法士の立場として、また発達障がい乳幼児とリスク児の発達支援、その家族を支援する『こども発達支援センター』の学園長としての立場でお話しをされた内容を要約いたします。
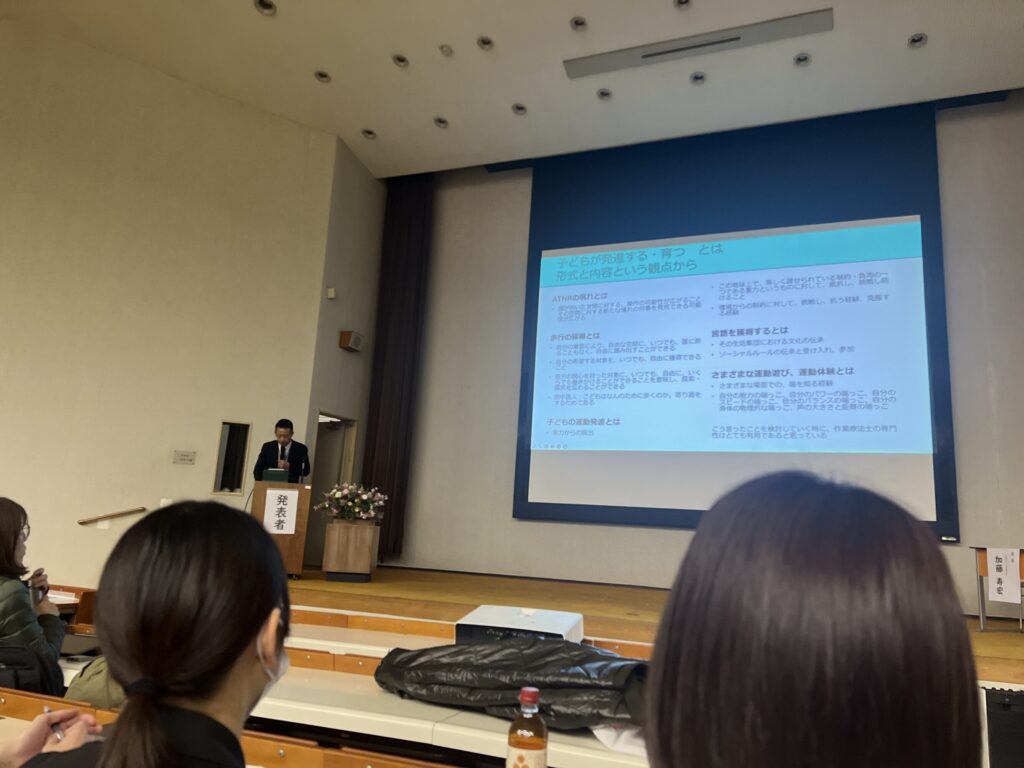
■酒井康年先生 ご講演要約
本講演では、発達系作業療法(以下、発達OT)を取り巻く社会的状況と、そこに期待される作業療法士(以下、OT)の役割、そして実践上の課題や今後の展望が示された。特に「地域の場」での子ども支援が重要視されていること、さらには学校や学童保育、保育園など多様な教育・保育現場においてもOTの専門性が広く求められ始めている点が強調されている。
【1.発達OTの拡大する就業領域と課題】
従来、OTの仕事場は医療機関が主であったが、児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害福祉領域における需要が急速に増え、OT求人が拡大している。しかし、その需要増が必ずしも「OTの専門性を十分理解したうえでの配置」とは限らず、「OTを配置すれば加算が得られるから」という表面的な理由で雇用されるケースも存在する。結果として、現場に先輩OTが不在、一人職場で支援体制が乏しい、職員全体がOTの強みを認識していないといった状況に直面し、新卒や若手OTが早期に離職してしまう例も少なくない。
こうした「OTの専門技術を発揮しにくい職場構造」や「人材育成が不十分な環境」が増えていることが、発達OT領域の質の担保という面で懸念されている。また、医療以外の地域領域へ参入するOTが急増する一方、各都道府県の作業療法士会は「派遣先を求める行政や施設」からの要請に人材を十分に派遣できない事態も生まれている。OT全体の絶対数は増えているが、専門的な発達OTとして活躍できる人材が地域ごとに偏在していることも指摘される。
【2.学校作業療法の広がりと日本独自の制度との整合】
2016年に日本作業療法士協会として「学校作業療法」という言葉を公式に用い始めて以来、特別支援学校だけでなく、通常学級や通級指導教室、学童保育の現場などでもOTを導入しようとする動きが見られるようになってきた。海外のスクールOT(School-based OT)に倣った取り組みもあるが、国ごとに教育制度が異なるため、日本の学校にOTが入り込む際には、日本の教育制度特有の仕組み(例:特別支援教育の枠組み、保育や学童保育の制度など)を深く理解したうえで活動内容を設計する必要がある。
一方、海外のように制度の後押しが十分でない日本では、公的支援があったとしても非常勤枠が中心となり、安定した給与や雇用形態を確保できないケースも多い。こうした雇用面の課題が、発達OTとしての専門性を高めようとする人材の獲得・育成を阻む一因となっている。
【3.「子どもの発達」とは何か?形式と内容の視点】
本講演では、子どもの発達を単に「できるようになる」マイルストーン(形式)だけで捉えるのではなく、その裏にある「子どもが世界と関わりながら育っていくプロセス」(内容)に着目する重要性が説かれている。例えば、子どもが「歩く」ことを獲得した際には、目的地へ向かうという形式的な動きだけでなく「重力に挑戦し、空間を探検し、自分の意思を自由に実現していく経験」を積む意味がある。また、言語の獲得も、文化的・社会的文脈のなかで自分を表現し他者と関わる力を手にしていく営みとして捉えられる。
こうした「発達の内容」を踏まえると、発達の遅れや障害が生じると、単に機能面で不利があるだけでなく、「子どもが本来は得られるはずの挑戦や発見の機会」が奪われてしまう。それゆえ作業療法士は、機能訓練やマイルストーン達成の手助けに終始するのではなく、子どもの「内的衝動」や「憧れ」が引き出され、社会や環境との相互作用が活性化するよう支援することが鍵となる。
【4.作業療法の専門性―サイエンス&アートとしての実践】
作業療法の哲学的基盤として「人は作業を通じて健康と幸福を獲得する」という信念があり、ICF(国際生活機能分類)が重視する「活動と参加」をいかに支援するかが中心となる。本講演では、「サイエンス&アート」としての作業療法技術が特に強調された。サイエンスとしての面は、根拠に基づくアセスメントや分析、段階付けなど、論理的・体系的な支援プロセスに見られる。一方、アートとしての面は、対象となる子ども一人ひとりの「隠された力」を引き出すために必要な「巧みの技」(環境調整やかかわり方、活動の創意工夫など)を発揮し、子どもの発達の内容を実感できるよう導く創造性を指している。
また「技術」とは単なる手段ではなく、真の姿を顕現させるための働きかけ――すなわち子どもの本質的な力を見抜き、それを活かす環境を設定する行為でもある、という視点が述べられた。
【5.今後の方向性と課題】
こうした発達OTの需要と専門性の高まりに対し、協会や各都道府県士会が現場からの依頼(行政・教育委員会・福祉施設など)に応えきれないケースも増えている。現在、専門的な「発達OT」の人数が限られる一方で、新たに「子ども分野を始めたい」というOTが増えている。いわゆる“ジャナイOT”(成人領域や精神領域など別領域が専門だが、地域からの要請で児童支援に携わることになった人々)が果たす役割は大きいが、知識・技術を十分に補完する仕組みづくりや研修の充実が急務である。
特に若手OTの自己研鑽が進みにくい風潮(研修会参加への意欲低下、本を読まないなど)が社会全体の課題として指摘される中、作業療法士会や教育機関が指導・育成プログラムを整備する必要がある。さらに、職域拡大への期待が続く一方で、質の担保・専門性の維持向上には「作業療法の本質とは何か」を各現場やOT自身が再確認することが欠かせない。
講演者は、「全ての子どもの可能性を形にする」ことを目標に掲げ、作業療法のサイエンス&アートを活かした支援を深化させていくことの大切さを強調している。そして「形式(機能や能力)」だけでなく「内容(子どもの内なる力、憧れや挑戦への意欲)」を重視し、子どもの社会参加や家族の幸福につながる実践を積み重ねる必要があると述べた。今後も、専門店のような高度技能をもつ発達OT(いわば“三ツ星レストラン”)を全国各地で増やしつつ、幅広い領域のOTが協力し合って子ども支援を支える体制を築いていくことが急務だと締めくくられています。



