株式会社キングジム本社を山本博司前参議院議員と訪問 宮本会長らと懇談:東京都
17日午後、株式会社キングジム本社を山本博司前参議院議員と訪問いたしました。
キングジム社の宮本彰会長、堀井信之経営企画部長、赤川和樹企画課長と、障害者福祉・就労などで多岐に渉り意見交換させて頂きました。
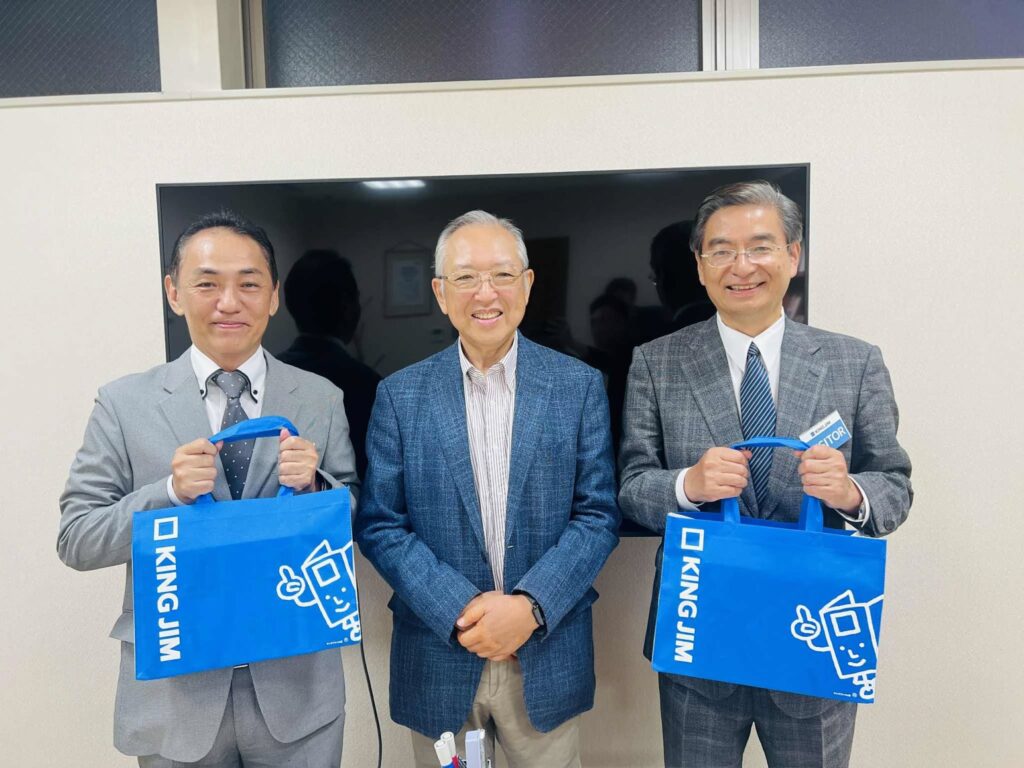
1927年創業。「キングファイル」「テプラ」など、パイオニアとして新しい市場を開拓してきたキングジム。
「独創的な商品を開発し、新たな文化の創造をもって社会に貢献する」を経営理念とし、新時代を切り拓く製品作りをされています。
宮本彰会長は1988年に「テプラ」発案され、キングジム社のパイオニア的な製品になりました。
その後 32年間同社の代表取締役社長を務められました。
現在では会長職となって、社会貢献を真剣に考えられておられ「何か障害福祉に貢献できないものか?」ということを、慶應大学時代の同期であった山本博司氏に相談され、本日の懇談が実現しました。
【宮本 彰 氏のプロフィール】 キングジム取締役会長
1954年東京生まれ。慶應義塾大学卒業後にキングジムに入社。84年に常務取締役総合企画室長、86年に専務取締役に就任。85年にそれまで自社で扱っていなかった電子文具の開発を目指す「Eプロジェクト」を立ち上げ、88年に発売した「テプラ」は大ヒット商品となりました。
92年に代表取締役社長に就任。「ポメラ」「ショットノート」をはじめ、独創的なアイデア商品を次々とヒットさせています。
昨年9月から会長に就任されています。
以下が懇談内容の要約となります。なお、以下の文面の文責は、すべて特定非営利活動法人輝HIKARIにありますので、懇談内容について、キングジム社への問い合わせはお控えください。
社会貢献への意志と三者の邂逅
株式会社キングジムの宮本会長、前参議院議員の山本博司氏、そして障害福祉サービスを提供するNPO法人「輝HIKARI」の代表理事である金子訓隆氏。この三者による懇談は、一企業の社会貢献への真摯な問いかけから始まった。キングジム社として、自社の製品を通じて障害のある子どもたちのために何か貢献できないか──。この宮本会長の思いが、慶應大学の同期である山本博司氏へと繋がった。山本氏は、自身も障害を持つ娘の親であり、国会議員として18年間にわたり、障害者福祉の政策推進に心血を注いできた人物である。その山本氏の紹介により、現場の最前線で活動する特定非営利活動法人輝HIKARIの金子訓隆氏が同席する形で、この意義深い会談が実現した。企業の社会的責任、政治の役割、そして福祉現場の現実という三つの異なる視点が交差し、具体的な支援の形を模索する対話が、静かに幕を開けた。
第1部:障害福祉の最前線──政策の光と現場の現実
懇談は、まず山本博司氏が自身のこれまでの歩みと、日本の障害福祉政策の現状を語ることから始まった。山本氏は、公明党の議員として18年間にわたり活動し、特に厚生労働分野をライフワークとしてきた。議員生活18年の間に、障害者の文化芸術振興法や発達障害者支援法など、合計29本もの障害者関連の法律制定に中心的な役割を果たした。その背景には、常に障害を持つ自身の娘の存在があった。彼の政策への情熱は、単なる政治活動に留まらず、一人の親としての切実な願いが原動力となっていたのである。
「私が議員になった当初、国の障害福祉関連予算は5000億円程度でした。それが今や4兆2000億円、約8倍にまで増やすことができました」
山本氏は、具体的な数字を挙げながら、国政の場で障害者福祉が着実に前進してきたことを強調した。しかし、公明党が定める69歳の定年制により、惜しまれつつも政界の一線を退くこととなった。だが、彼の活動が終わったわけではない。がんセンターの医師であった原田大二郎氏を後継者として、自身は議員OBという立場から、今なお政策提言や現場との連携を精力的に続けている。
その山本氏が「同じ障害の親の立場」として絶大な信頼を寄せるのが、NPO法人輝HIKARIの代表理事、金子訓隆氏である。金子氏は、もともとシステムエンジニアとしてIT業界に身を置いていたが、知的障害を持つ息子が生まれたことを機に、福祉の世界へ足を踏み入れた。右も左もわからぬ中、地元の議員を通じて紹介されたのが、当時現職の参議院議員であった山本氏だった。
「2012年の2月、初めて山本先生の国会事務所を訪ねました。障害のある子どもを持つ父親という同じ立場で、制度改革を一緒に取り組んでほしいとお願いしたのです」
その時、山本氏から手渡された一冊の手記『ひびき』が、金子氏の人生を大きく動かした。「利権ではなく、本当に人にテーマを当てている国会議員がいる」。感銘を受けた金子氏は、以来13年間にわたり、山本氏と共に全国22の都道府県を巡り、300回以上の活動を共にしてきた。
金子氏の活動の中核を成すのが、2012年の法改正によって制度化された「放課後等デイサービス」である。これは、学校終了後や夏休みなどの長期休業日に、障害のある子どもたちを預かる学童保育のような事業だ。金子氏自身の息子も、小学校入学時に行き場所がなく、妻が仕事を辞めざるを得ない状況に直面した。「ないんだったら作ろう」。その一心で私財を投じて施設を立ち上げ、13年経った今では8つの事業所を運営し、約50名の職員を抱えるまでに成長した。
しかし、現場の運営は決して順風満帆ではない。金子氏は、厳しい実情を吐露した。
「ここ数年、電気・ガスなどの光熱費や物価の高騰、そして職員の賃金上昇が続いています。しかし、国から事業所に支払われる一人当たりの報酬単価は3年に1度の改訂です。営利目的で参入した事業者は、いま採算が合わずに次々と撤退している現状です」
NPO法人である「輝HIKARI」は、法人税の減免措置を受けているが、より多くのサービスを提供できるよう、運営費や全国での障害福祉支援活動に充てている。そこで、施設での必需品であるファイルや文房具といった備品は、全て法人の負担で購入しており、ネットで安価な物を探しては必死に経費を切り詰めているという。
政策という大きな枠組みが光を当てる一方で、その光が届きにくい現場の隅々には、物価高騰や子どもの貧困といった切実な課題が横たわっている。山本氏が築き上げた制度の土台の上で、金子氏のような現場の実践者が日々奮闘している。この両者の言葉から、日本の障害福祉が持つダイナミズムと、同時に抱える脆弱性が浮き彫りになった。宮本会長は、二人の話に静かに、そして真剣に耳を傾けていた。
第2部:具体的な支援の形──現場のニーズと企業の可能性
障害福祉の現場が直面する課題を共有した後、対話の焦点は「キングジムとして具体的に何ができるか」という本題へと移っていった。宮本会長が「どういう形でのご貢献ができるか、ぜひお聞かせください」と促すと、金子氏は、施設現場で必要としている製品を具体的に挙げ始めた。
「やはり、御社の代名詞である『テプラ』と『ファイル』は、私達にとって必需品です」金子氏によれば、事業所では利用者一人ひとりに関する支援記録や個人情報を、利用される方によっては、10年以上にわたって厳重に管理する必要がある。そのため、堅牢で使いやすいキングジムのファイルは、大量に消費されるという。また、テプラは、子どもたちの名前をロッカーや靴箱に貼ったり、施設の備品に用途を表示したりと、視覚的な支援が不可欠な発達障害の子供たちのために、ありとあらゆる場面で活用されている。
さらに、療育活動で使うシールや、集団活動の際に時間の経過を視覚的に分かりやすく示すためのカレンダーやタイマーなど、金子氏はキングジムのカタログを事前に読み込んできたかのように、具体的な製品名を挙げてその必要性を熱心に説明した。
コンパックノートは、保護者との連絡帳で使うメモを保管するのに最適であり、マスキングテープは子供たちの創作活動(壁面製作)で活用できるという、現場のニーズに合致する素晴らしいアイデアだった。
こうして、企業の論理と現場のニーズが巧みにすり合わされ、金子氏が窓口となり、キングジム社の担当者と納品に向けた実務的な調整を進めるだけとなった。企業の持つリソースと、福祉現場の切実な声が、確かな形で結びついた瞬間だった。
第3部:対話が拓く未来──就労、アート、そして共生社会へ
対話は、単なる物品支援に留まらず、障害者福祉の未来、そしてよりインクルーシブな社会のあり方へと広がっていった。
山本博司氏が、議員を引退した今、新たに取り組んでいるテーマとして「就労困難者への支援」を挙げた。これは、ひきこもりや難病患者など、現在の障害者雇用制度の枠組みでは支援が届きにくい人々を対象とした、新たな法制度の創設を目指す活動である。
「今の制度だと、なかなか就労に結びつかない方々がたくさんいます。これを『ダイバーシティ就労』という形で制度として作り、支援したい。議員OBになっても、現議員と協力しながら、議員連盟を立ち上げていき法律の制定を目指したいと思っています」
この構想の鍵を握るのが、デジタルの力だ。宮本会長の話から山本氏は、在宅で寝たきりの難病患者や脊椎損傷の患者が、遠隔操作ロボットを介してカフェの店員として働く「分身ロボットカフェ」の事例を紹介した。自宅のベッドの上から、目線の入力だけでロボットを操作し、客から注文を取る。身体的な制約があっても、テクノロジーを活用することで社会と繋がり、働くことができる。この革新的なビジネスモデルは、就労困難者が持つ無限の可能性を示している。金子氏も、「生産労働人口としてカウントされていない就労困難者の方々は、全国に障害のある方も含めて約255万人いると言われています。こうした方々が少しでも社会に出てきていただくための仕組み作りが急務です」と、山本氏の取り組みを後押しした。
宮本会長は、障害者支援は、単なる社会貢献活動ではなく、新たな市場やイノベーションを生み出す可能性を秘めている。その気づきは、企業のトップとして重要な視点であった。
さらに、話題は障害者の持つ芸術的な才能、いわゆる「アール・ブリュット」へと展開した。山本氏は、自身が制定に関わった障害者文化芸術活動推進法がきっかけとなり生まれた。
「障害のある方が描いたデザインを商品化し、売り上げの数パーセントがライセンス料として本人に支払われる仕組みです。彼らの持つ、我々にはない研ぎ澄まされた感性が、ビジネスとして成功し、本人の経済的自立にも繋がっているのです」
この話は、障害者を「支援の対象」としてだけでなく、社会に新たな価値を生み出す「才能の源泉」として捉える視点の転換を促した。
宮本会長も、キングジム社が過去に取り組んだ挑戦について15年ほど前に開発した「点字テプラ」があった。テプラのテープに点字を打刻できる画期的な製品だったが、当時は時期尚早だったようにも見受けられたが、この話に、山本氏と金子氏は「今なら、ものすごく需要があると思います」と口を揃えた。視覚障害者が通う盲学校は各県に一つ程度しかなく、卒業後の就労先も鍼灸師などに限定されがちだ。しかし、彼らは点字を読み解くプロフェッショナルである。点字テプラがあれば、彼らがそのスキルを活かせる新たな仕事が生まれるかもしれない。過去の挑戦が未来への種となる可能性を感じ取っていた。
懇談は、具体的な物品の寄付という入口から、就労支援、アート、テクノロジーの活用、そして新たなビジネスモデルの創出まで、障害者福祉を取り巻く多岐にわたるテーマへと深化していった。それぞれの立場から知見を出し合い、共生社会の未来を共に構想する創造的な対話であった。
この懇談は、キングジムという一企業の社会貢献への真摯な思いが、山本博司という政治家の情熱とネットワークによって福祉の現場へと繋がり、金子訓隆という実践者の切実な声と結びつくことで、具体的な成果を生み出した稀有な事例となった。それは、企業の持つリソース、政治の持つ推進力、そして現場の持つ知見が、それぞれの役割を果たし、見事に噛み合った結果であった。
対話を通じて、障害福祉の現状と課題が共有され、就労や山本氏は「こういう機会をいただいて、本当にありがたい」と感謝を述べ、宮本会長は「素晴らしいお二方だなと思います。」と応じた。
言葉だけの約束ではない、この小さな一歩が、障害のある子供たちの日常を少しでも彩り、ひいては誰もがその人らしく輝ける社会を築くための、大きな礎となることを期待したい。最後の三者の記念撮影での笑顔が、その明るい未来を予感させていた。






“株式会社キングジム本社を山本博司前参議院議員と訪問 宮本会長らと懇談:東京都” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。