知的・発達障害児・者への歯科治療について(3)
知的・発達障害児・者への歯科治療について(3)
このコラムは以下の(1)と(2)の続きです。
今回は、日本障害者歯科学会の発足とその歴史、現在の活動と理解促進に向けた支援活動や取り組みについて書きます。

日本障害者歯科学会の発足とその歴史
日本障害者歯科学会(Japanese Society for Disability and Oral Health, JSDH)は、障害者の口腔保健を専門に扱う日本最大の学術団体であり、その歴史は障害者歯科のニーズが社会的に認識され始めた時期に遡ります。
発足の経緯
学会の起源は、1973年(昭和48年)に設立された「日本心身障害児者歯科医療研究会」にあります。この研究会は、心身障害児・者の歯科治療に関する研究と実践を目的として、歯科医師や関連医療従事者によって組織されました。当時、障害者の歯科医療は一般の歯科治療とは異なる特別な配慮が必要であるにも関わらず、体系的な取り組みが不足しており、こうした状況を改善するために有志が集まったことがきっかけです。特に大阪府歯科医師会が1960年代から取り組んでいた障害者向けの歯科診療活動が、研究会の設立に大きな影響を与えました。
学会への発展
1984年(昭和59年)、研究会は活動の拡大と専門性の強化を目指し、「日本障害者歯科学会」に名称を変更しました。この改称は、障害者歯科を単なる慈善活動から、学術的・専門的な分野として確立する意志を反映したものです。学会はその後、全国的なネットワークを構築し、障害者の口腔保健に関する研究、教育、実践の中心的な役割を担うようになりました。
主な歴史的節目
•1999年(平成11年): 日本歯科医学会の専門分科会として認定され、障害者歯科が正式に歯科医療の一分野として認められました。
•2003年(平成15年): 認定医制度が導入され、障害者歯科に特化した専門家の育成が始まりました。
•2008年(平成20年): 認定歯科衛生士制度が開始され、歯科医師だけでなく衛生士の専門性向上も図られました。
•2017年(平成29年): 専門医制度が導入され、より高度な知識と技術を持つ医療者の認定が進められました。
現在、学会の会員数は約5,000名(2023年時点の公式発表に基づく)に達し、歯科医師、歯科衛生士、研究者、福祉関係者などが参加する多職種連携の組織へと成長しています。
現在の活動
日本障害者歯科学会は、障害者の口腔保健を向上させるために多岐にわたる活動を展開しています。以下に主要な活動を詳述します。
- 学術研究と学会開催
学会は年1回の学術大会を開催し、最新の研究成果や臨床事例を共有しています。2023年の第40回学術大会では、「障害者の生涯を通じた口腔健康管理」をテーマに、摂食嚥下障害や高齢障害者のケアに関する発表が行われました。また、学会誌『障害者歯科』(年4回発行)を刊行し、研究論文や症例報告を通じて知識の普及を図っています。 - 専門人材の育成
認定医・専門医制度や認定歯科衛生士制度を通じて、障害者歯科に特化した医療従事者の養成を進めています。これらの資格は、一定の研修受講と試験を経て取得可能で、例えば専門医には5年以上の臨床経験と学会発表の実績が求められます。2023年時点で、認定医は約500名、専門医は約100名が登録されています。 - 臨床ガイドラインの策定
障害者歯科における治療やケアの標準化を目指し、『障害者歯科臨床ガイドライン』を策定・改訂しています。このガイドラインでは、全身麻酔下での治療や行動調整法、口腔ケアの具体的な手法が記載されており、医療現場での実践を支援しています。 - 地域連携と支援活動
全国の歯科医師会や福祉施設と連携し、地域での障害者歯科診療をサポートしています。例えば、「障害者歯科診療所」の設置を自治体に働きかけたり、訪問歯科診療の普及を推進したりしています。また、重度障害者向けの治療に対応する「障害者歯科医療連携施設」のネットワーク構築にも取り組んでいます。
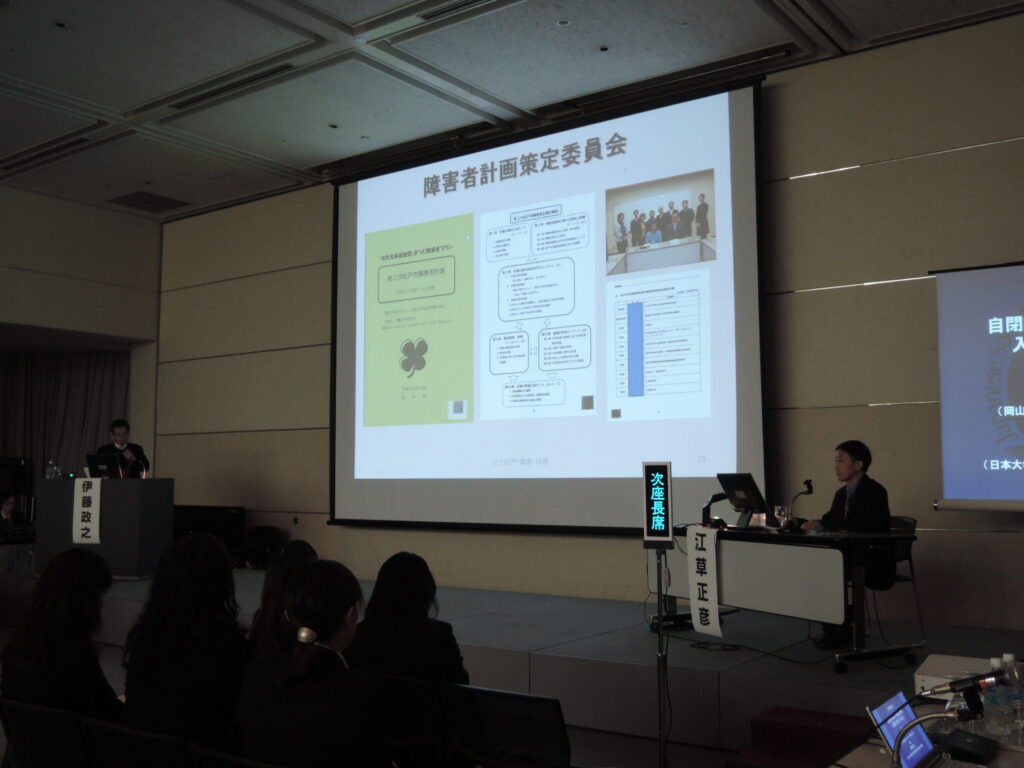
理解促進に向けた支援活動と取り組み
障害者歯科の重要性を社会に広め、実践を促進するために、学会は以下のような支援活動や取り組みを行っています。
- 啓発キャンペーンと市民向け教育
障害者やその家族、一般市民に向けた口腔保健の啓発活動を実施しています。例えば、「お口の健康フェア」などのイベントで、障害者の口腔ケアの重要性や具体的な方法を伝えるワークショップを開催しています。また、学校や福祉施設向けに講師を派遣し、教員や介護職員への教育も行っています。 - 障害者と家族への支援
学会は、障害者やその家族が歯科治療にアクセスしやすくするための情報提供を行っています。公式ウェブサイトでは、全国の障害者対応可能な歯科医院リストや相談窓口を公開しており、治療のハードルを下げる努力を続けています。また、保護者向けに「障害児の口腔ケアハンドブック」を配布し、家庭でのケアをサポートしています。 - 医療従事者への意識改革
一般の歯科医師が障害者歯科に抵抗感を持たないよう、研修会やセミナーを開催しています。これにより、障害者の治療を「特別なもの」と捉えず、日常診療に取り入れる意識を醸成しています。特に若手歯科医師向けの「障害者歯科入門コース」は、参加者が年々増加しています。 - 政策提言と政府との連携
厚生労働省や日本歯科医師会と協力し、障害者歯科の制度改革を推進しています。例えば、保険診療での報酬加算や、障害者歯科診療所の公的支援拡充を求める提言を行っています。2022年には、「障害者の口腔保健向上に関する提言書」を政府に提出し、超高齢社会に向けた施策の必要性を訴えました。 - 国際交流とグローバルな視点
国際障害者歯科学会(International Association for Disability and Oral Health, IADH)との連携を強化し、海外の先進事例を取り入れています。例えば、英国やオーストラリアの障害者歯科モデルを参考に、日本独自のシステム構築を目指しています。また、アジア太平洋地域の学会とも交流を持ち、国際的な視点での理解促進に努めています。
まとめ
日本障害者歯科学会は、1973年の研究会発足以来、障害者の口腔保健を支える中核組織として発展してきました。現在の活動は、学術研究や人材育成、地域支援に重点を置きつつ、啓発や政策提言を通じて社会全体の理解を深める取り組みに広がっています。これらの努力は、障害者が健康で豊かな生活を送るための基盤を築くだけでなく、インクルーシブな社会の実現に向けた重要なステップとなっています。学会の今後の課題は、地方での支援体制の強化や、新技術の活用を通じたアクセスの拡大にあると言えるでしょう。





