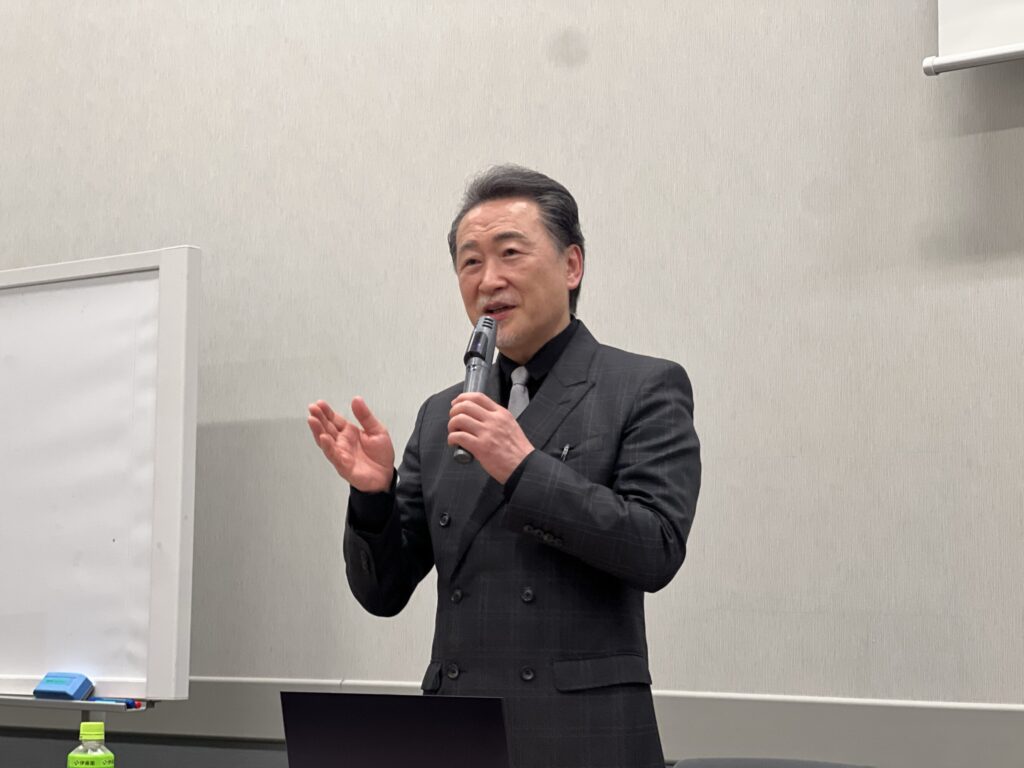第38回 Bluesky勉強会「筋肉革命95」講演:酒向 正春氏
6日夕方から参議院議員会館にて、第38回BLUESKY勉強会が開催されました。
Bluesky勉強会は平成26年(2014年)8月に第1回の勉強会を開催以来、ICTの利活用など情報通信の分野を中心に、これまで37回にわたり議論を進めてまいりました。当団体の金子訓隆代表理事は、本勉強会の事務局を担当しており、第一回目の開催から参加しています。
今回の第38回勉強会は、会場とリモートのハイブリッドで行い合計約80名の方が参加いただきました。
【内容】
挨拶:山本博司前参議院議員・原田大二郎参議院議員
講演:「筋肉革命95で世界の高齢社会にイノベーションを起こす」講師:酒向 正春氏 / 大泉学園複合施設 ねりま健育会病院院長・回復期リハビリテーションセンター長
1.後遺障害をどのように回復させるか
2.攻めのリハビリとは
3.後遺障害後を一生支える日本のリハ医療体制
4.後遺障害に寄り添う街づくり/タウンリハ
5.95歳で非介護、80歳で8割就労が世界貢献
現在練馬区の大泉学園複合施設「ねりま健育会病院」の院長を務められ、2017年8月にも視察。同年10月には「Bluesky 第17回勉強会」でも講演。
「筋肉革命95」は、NHK視点論点・「羽鳥慎一モーニングショー」はじめ、数々の新聞・雑誌・テレビでも取り上げられています。9月9日付け公明新聞にも掲載されました。

挨拶:山本博司氏
山本氏はまず、勉強会が2014年の開始から11年目、38回目を迎えたことを報告。自身は7月に参議院議員を勇退しており、OBとして初めての開催となりました。勉強会はもともと愛媛県関係者を中心に、「坂の上の雲」を超える思いで発足しましたが、現在は原田大二郎氏に引き継がれ、地域課題や社会課題に関する政策提言などを目指し継続されています。当日は対面とリモートを合わせ、島根、大阪、愛媛などから約80名が参加しました。
続いて、講師の酒向正春先生について紹介されました。酒向先生は1961年、山本氏の故郷・八幡浜市の隣である愛媛県宇和島市の出身。1987年に愛媛大学を卒業後、脳卒中治療の第一線で活躍し、デンマークの研究所への留学経験もあります。2004年、43歳でリハビリテーション分野に進むことを決意し、世田谷記念病院の副院長や回復期リハビリテーションセンター長などを歴任されました。酒向先生の登壇は、2017年の第17回以来2回目となります。山本氏は、過去に世田谷病院を視察したことや、公明党の地域包括ケア推進本部で「攻めのリハビリ」などをテーマに講演を依頼した経緯にも触れ、長い縁に感謝を述べました。酒向先生は、現在「モーニングショー」やNHK「視点・論点」などメディアでも活躍する多忙の中での登壇であり、本日のテーマである予防医療などについて、しっかり話を聞きたいと期待を寄せました。
挨拶:原田大二郎参議院議員
第38回Bluesky勉強会に、会場およびウェブからご参加いただき、誠にありがとうございます。
私、原田大二郎は、この夏の参議院選挙におきまして、皆様の多大なるご支援をいただき、山本博司氏の後継として初当選させていただきました。医療、介護、障害、福祉、保育など、様々な分野で本当に困っている方々のためにしっかりと成長していく決意で、今まさに走り出したところです。
この勉強会では、様々な分野の先生方から新しい発想やアイデアをいただき、それを政策に活かしていくことを目指しております。
本日ご講演いただく酒向正春先生は、私の母校である愛媛大学医学部の大先輩であり、心から尊敬しております。酒向先生は脳神経外科医として素晴らしい功績を上げられる中で、早くからリハビリテーションの重要性に着目されました。脳梗塞などの手術で命が助かっても、その後元気に働き、人生を謳歌するためにはリハビリの力が必要だと、その活動に全力を注いでいらっしゃいます。
ご著書『筋肉革命95』は、高齢であっても活躍できるという新しい人生観を提案するベストセラーとなり、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」でも取り上げられるなど、日本中に希望を与えています。
私自身も呼吸器内科医として20年、がん患者さんなど多くの方を診てまいりました。治療の発展も重要ですが、それと同時に「予防医療」がこれからの時代の要請であると痛感しております。
公明党も食事、運動、生きがいづくりを重視しています。本日の酒向先生のお話は、まさに私が取り組みたい予防医療の核となるテーマです。しっかりと学ばせていただき、これからの政策に反映できるよう全力で頑張ってまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
以下は、酒向正春先生の講演「筋肉革命95:世界の高齢社会にイノベーションを起こす」の要約です。
講演「筋肉革命95」要約
講師紹介とテーマ
第38回Bluesky勉強会における酒向正春先生(健育会ねりま健育会病院院長)の講演。酒向先生は脳卒中治療の専門医として38年のキャリアを持ち、デンマークでの脳科学研究、リハビリ専門医としての経験、NHK「プロフェッショナル」出演、シンガポールでの高齢社会イノベーションに関する講演など、国内外で活躍。2003年からはライフワークとして「まちづくり」にも取り組んでいる。
本講演のテーマは「筋肉革命95」。95歳で要介護、80歳で8割が就労や家事を担う社会を目指すというビジョンに基づき、脳卒中後遺症の回復可能性、独自のリハビリ手法(攻めのリハ)、日本のリハビリ体制、まちづくり、そして「筋肉革命」の科学的根拠について解説された。
脳卒中後遺症とリハビリの可能性
講演の核心は「諦めないリハビリ」と「科学的評価」である。酒向先生は、回復が困難とされた重度の患者が劇的に改善した複数の事例を紹介した。
- 62歳男性(脳出血):
手術後7ヶ月間寝たきり、経管栄養、気管切開の状態。他院では「これ以上は無理」と言われた。しかし酒向先生が脳画像を解析したところ、脳の損傷自体は寝たきりになるほど重度ではなく、「寝たきりにされてしまった」状態だと判断。
結果:立たせて歩かせ、コミュニケーションを図るリハビリを実施。2ヶ月で経管栄養が外れ、自分で食事をし、介助で歩行・トイレが可能になった。これは奇跡ではなく科学的評価に基づく結果である。 - 91歳女性(脳腫瘍術後):
左足切断、右目失明。主治医からは車椅子生活を宣告された。しかし、脳画像では脳の萎縮はあっても大きな損傷はなく、認知機能(MMSE)も21点あったため、回復可能と判断。
結果:立位・歩行訓練というシンプルなリハビリで、義足で歩いて退院した。 - 93歳女性(感染症):
感染症で寝たきりになり、15cmの褥瘡(じょくそう)ができた。脳の損傷は少なく、MMSEは25点。
結果:車椅子で来院したが、退院時には介助で歩行可能となり、MMSEも満点の30点に改善した。
これらの事例から、重要なのは「脳画像を正しく評価し、回復の可能性を見極めること」であり、年齢や重症度で諦めてはならないことが示された。
「攻めのリハ」:科学的リハビリテーション
酒向先生が提唱する「攻めのリハビリ(Sako Method Rehabilitation)」は、科学的根拠に基づく集中的なアプローチである。
1. 脳画像による精密な評価
20万例以上の脳画像解析経験から、脳の萎縮度や残存機能(特に運動神経である錐体路の状態など)を詳細に分析し、回復の限界点を予測する。この研究成果は「Nature」のオンラインジャーナルにも掲載された。
2. 回復を最大化する「3つの基盤」
日本のリハビリ病院の多くが実施していない、以下の3点を徹底する。
- 3時間のリハビリ:厚労省基準の最大単位(これは多くの病院で実施)。
- 12時間の完全離床:日中はベッドから離れて座った状態を維持する。
- 24時間の全身管理:再発予防と全身状態の管理を徹底する。
3. チーム医療と重症者へのアプローチ
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)だけでなく、看護師、薬剤師、ケアワーカー、歯科衛生士、管理栄養士など多職種が連携する。
特に46歳男性の脳腫瘍術後の重症例では、手足が固まって(拘縮)リハビリができない状態だったが、脊髄に直接薬剤を投与する「バクロフェン髄注療法(ITB療法)」で筋肉を緩め、「立たせる」訓練を可能にした。結果、意識が改善し、8ヶ月で復職に至った。
4. 回復を妨げる要因の排除
高齢者が10種類以上の薬を服用する「ポリファーマシー」の状態では回復が阻害される。薬を6種類以下に減らすことでリハビリ効果が高まることも論文で発表している。
社会復帰と「まちづくり」
リハビリのゴールは退院ではなく、社会復帰(復職)と生活の質の維持である。
復職への8つの条件
退院後、自宅の情報過多(テレビ等)により「うつ」になる患者が多い。復職には「障害を理解する支援者」や「情報を単純化する工夫」が必要であり、以下の8条件を満たす必要がある。
- 病状の安定
- 本人の就労意欲
- 身の回りのことが自立
- 感情のコントロール
- 障害の自己説明が可能
- 障害を代償して就労可能
- 自力での通勤
- 週4〜5回の就労
病院はこれらを見据えて入院中から退院後まで継続的に支援する必要がある。
健康を支える「まちづくり」
酒向先生のライフワークは、リハビリとまちづくりの融合である。「社会参加や社会貢献が健康寿命を伸ばす」という2003年からの提唱は、2023年に「Nature」誌によっても証明された。
- ハード(国土交通省):社会参加しやすい環境整備。
- ソフト(厚生労働省):社会参加を支援する体制。
これを「タウンリハビリテーション」と呼び、居場所・生きがい・役割の創出を目指す。
- 実践例(八重洲・双子玉川):歩道の拡幅(千南アプローチ)や、病院とショッピングモールを連携させたリハビリ環境の構築。
- 実践例(練馬区):「お金をかけないまちづくり」として、既存の公園、図書館、コミュニティセンターを活用。屋外歩行訓練や「チャイたび(近隣の庭を散歩する)」を実施し、結果的に地域の治安改善や活性化(カフェ等の出店)にも繋がっている。
「筋肉革命95」:世界への貢献
最終テーマは、健康寿命の延伸。目指すのは「80歳で要介護」ではなく、「80歳で8割就労・家事、95歳でそろそろ要介護」という社会像への転換である。
筋肉は90代でも育つ
50歳から年1%ずつ筋肉は落ち、80歳で2週間寝込むと10〜20%失い、一気に「寝たきり」になる。
しかし、筋肉は鍛えれば何歳でも育つ。90代のトレーニング実験では、2ヶ月で筋量12%増、筋力70%増を達成した。「脳は蘇らないが、筋肉は蘇る」点が重要である。
握力が示す「フレイル」の危険信号
約3,000例の入院患者データから、病気や怪我をしやすくなる「フレイル(虚弱)」の入口が判明した。
- 握力15kg以下:転倒リスクが極めて高い(80代女性に多い)。
- フレイルの目安:男性28kg以下、女性18kg以下(70歳前後でこの値になると要注意)。
筋肉が脳と身体を救う科学的根拠
筋トレ(3本メソッド:筋力増強、体力増強、バランス改善)が重要な理由は以下の通り。
- ホルモン分泌:筋肉から「マイオカイン」や脳の栄養因子「BDNF」が分泌され、脳を元気にする。
- 幹細胞の増加:修復細胞である「ミルト細胞」が増加する。
- 老廃物の除去:運動不足で筋肉内に蓄積する「難溶性タンパク質」は、薬や栄養では溶かせず、唯一「運動」によってのみ除去できる。
- 認知症予防:認知症の9つのリスク因子(糖尿病、高血圧、うつ、社会的孤立など)の多くは、運動によって改善可能である。
社会実装
この理論を社会に実装するため、愛媛県の離島・愛南町(人口1.7万人)に「筋肉革命ジム」を設立。人口の1%近い150人が入会し、地域住民の健康寿命がどう変わるかという社会的実験が始まっている。
結論
健康寿命の延伸には、科学的根拠に基づいた運動(筋肉革命)と、それを継続するための「楽しむこと」、そして「諦めない力」が不可欠であると締めくくられた。
【酒向正春先生プロフィール】
1961年宇和島市生まれで、愛媛大学医学部を卒業後、1987年脳卒中専門の脳神経外科医に。1997年~2000年デンマーク国立オーフス大学脳神経病態生理学研究所助教授を経て、40歳を過ぎてからリハビリテーション医へ転身。
脳画像から患者がどこまで回復可能かを読み取り、それに基づいて積極的な「攻めのリハビリ」を行うという独特の手法で驚くべき成果をあげ、長嶋監督やオシム監督をはじめ数多くの患者や家族から絶大の信頼を得ています。その真摯な仕事ぶりはNHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」でも取り上げられ、大きな反響を呼びました。
また「健康医療福祉都市構想」を提唱されています。「健康医療福祉都市」とは「高齢者・障がい者を含めた全ての市民が「まちで生活・社会参加」できる環境・市街地中心部からの健康と良質な生活のための都市」です。著書に「あきらめない力」があります。