筋萎縮性側索硬化症について
いま当団体の金子代表理事は、筋萎縮性側索硬化症について様々学んでいます。
今回のブログはこの筋萎縮性側索硬化症(ALS)について解説したいと思います。

筋萎縮性側索硬化症とは?
病名「Amyotrophic Lateral Sclerosis」
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、中枢神経系にある運動神経細胞が徐々に障害され、筋肉が萎縮していく進行性の神経疾患です。これにより、最初は手足の細かい動作に支障が出たり、歩行が困難になったりするなどの症状が現れ、病気が進むにつれて、全身の筋力低下や呼吸筋の衰えが起こることがあります。根本的な治療法はまだ確立されていませんが、薬物療法やリハビリテーション、呼吸管理などで症状の進行を遅らせ、患者さんの生活の質を維持するための対策が講じられています。
日本の現在の患者数(推計値)
最新の統計データは集計方法や診断基準によって多少の幅がありますが、近年の推計では、日本における筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者数はおおむね約1万人から1万5千人程度とされています。これは、ALSが比較的稀な疾患であること、また診断が確定するまでのプロセスや地域差などが影響しているためです。
なお、正確な数字については、厚生労働省や各都道府県の保健所、またALSに関する専門の研究機関や患者団体が公表する最新の統計情報を参照することが重要です。地域によっては、診断体制や報告方法の違いにより若干の差が生じることがあるため、最新情報の確認が推奨されます。
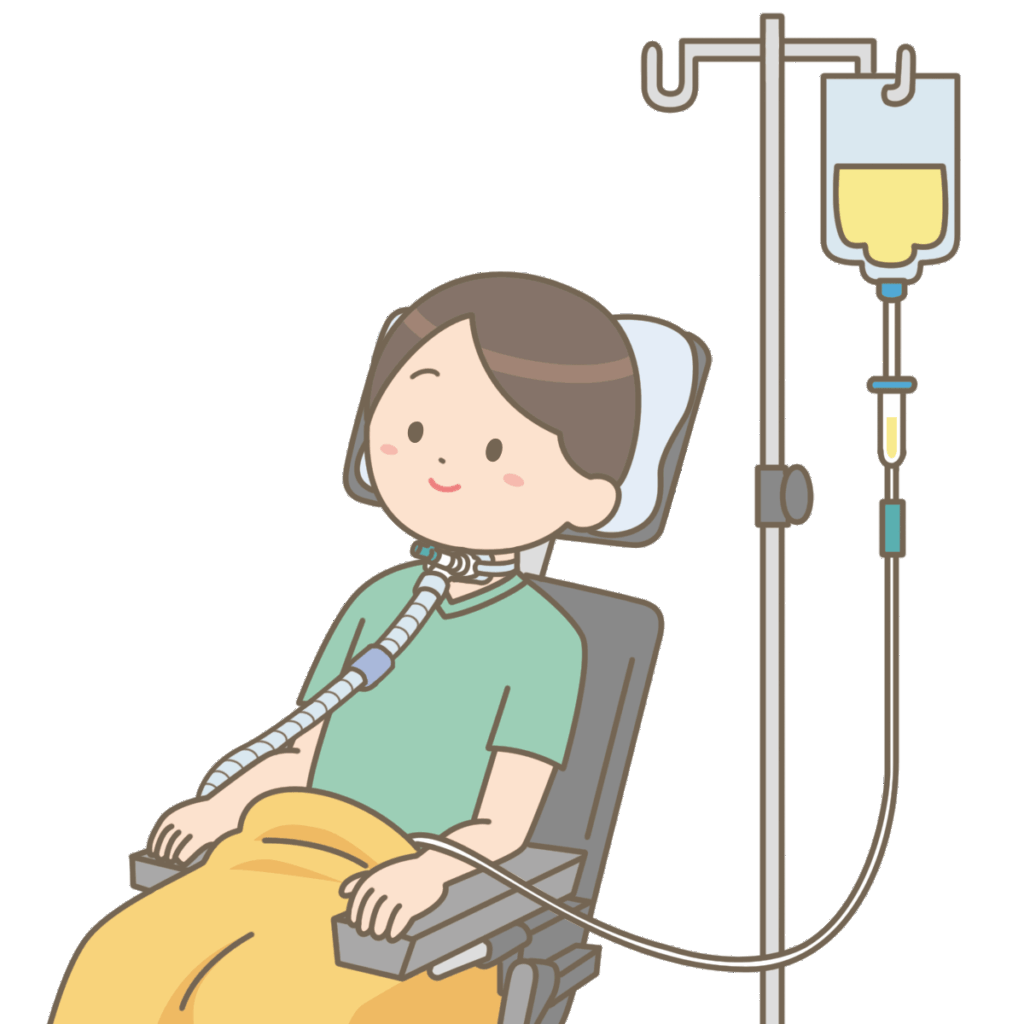
1. 初期症状と診断の流れ
ALSの初期症状は、まず筋力の低下や不自然な痙攣、筋肉の萎縮として現れることが多いです。具体的には、手足のふるえ、細かい作業が難しくなる、あるいは歩行時のバランスが崩れるなどの兆候が見られます。また、声のかすれや飲み込みにくさといった、いわゆる「嚥下障害」や「発音障害」が発症する場合もあります。これらの症状は、最初は軽微で日常生活に大きな支障をきたさないことが多いため、本人や家族が気付かない場合もあります。しかし、症状が徐々に進行するにつれて、診断のための神経学的検査、筋電図、画像診断などを通じて確定診断が下されるのが一般的です。
2. 病状の進行とその特徴
ALSは進行性疾患であり、症状は数ヶ月から数年のスパンで徐々に悪化していきます。初期段階では、局所的な筋力低下や痙攣が目立ちますが、病気が進むと四肢や呼吸筋にも影響が及び、歩行困難や日常生活動作の制限が顕著になります。特に呼吸筋が影響を受けると、呼吸補助装置の必要性が生じる場合もあります。進行の速度は個人差が大きく、一概に「この期間でこうなる」という予測は難しいものの、早期からの総合的なケアが重要とされています。
3. 治療方法について
現時点でALSの完治を可能にする治療法は確立されていませんが、症状の進行を遅らせたり、患者さんの生活の質を向上させるための治療やリハビリテーション、支持療法が行われています。
- 薬物療法
代表的な薬剤としては、リルゾールやエダラボンが挙げられます。これらは、神経細胞の損傷を抑制し、病気の進行をある程度遅らせる効果が認められており、症状管理の一環として用いられています。 - リハビリテーション
理学療法や作業療法を通じて、残された筋力や機能の維持・改善を図ります。個々の患者さんの症状や生活環境に合わせた運動療法が取り入れられることで、筋肉の硬直や痙攣の緩和、関節可動域の維持に寄与します。 - 呼吸管理と栄養管理
病気の進行に伴い、呼吸機能や嚥下機能の低下が懸念されるため、非侵襲的人工呼吸器の使用や経管栄養法、場合によっては胃ろう造設などが検討されることもあります。
4. 支援方法と生活の質向上のために
ALSは患者さんのみならず、家族や介護者にとっても大きな負担となる病気です。早期から以下のような支援体制を整えることが望まれます。
- 多職種チームによる包括的ケア
神経内科医、リハビリテーション専門家、言語聴覚士、栄養士、呼吸療法士、そして心理カウンセラーなど、多職種が連携して患者さんのケアを行うことで、症状の管理や精神的なサポート、社会生活への復帰支援が行われます。 - 社会資源の活用
地域包括支援センターやALS協会など、地域や国の支援団体からの情報提供や介護サービス、経済的支援、相談窓口の活用が推奨されます。これにより、介護負担の軽減や精神的な安心感を得ることが可能です。 - 家族・介護者へのサポート
家族は患者さんの最も身近なサポート役ですが、その負担も大きいです。家族会やサポートグループへの参加、専門のカウンセリングを受けることで、心理的な支援や情報交換が進むとともに、適切な介護方法の学習にも繋がります。 - 先進医療や地域医療との連携
進行性の病気であるため、定期的な診察や検査を通じて病状の変化に対応することが必要です。また、地域の在宅医療チームとの連携を強化することで、患者さんが住み慣れた環境で可能な限り自立した生活を送れるよう支援する取り組みも重要です。
まとめ
筋萎縮性側索硬化症は、初期には軽度な症状から始まり、徐々に全身に広がる進行性の神経変性疾患です。現時点で根本治療は確立されていないものの、薬物療法、リハビリテーション、栄養・呼吸管理といった多角的なアプローチにより、患者さんの生活の質の向上が図られています。加えて、多職種による包括的ケアや地域資源の活用、家族へのサポートを通じて、ALSに直面する患者さんとそのご家族がより良い環境で生活できるよう努めることが求められています。医療関係者や支援団体との連携を密にし、情報共有と早期対応を行うことが、今後のALSケアの大きなカギとなるでしょう。
また当事者の方とのコミュニケーションでは、重度障害者用意思伝達装置では、クレアクト社が開発・販売している「TC スキャン」という機器が用いられることがあります。
『TCスキャン』ならスイッチひとつで文章作成、メール、インターネット、パソコン操作ができます。補装具申請(公費*但し世帯の収入状況による)が可能な重度障害者用意思伝達装置です。
詳細は、クレアクト社ホームページで確認出来ます。
https://www.creact.co.jp/welfare/communication-device/tcscan/index.html
TC スキャンのデモ動画です。
瞳孔を検出し「人が何を見ているか」という視線計測を行う技術「アイトラッキング」でコミュニケーションを行います。
https://x.gd/aqqK4
いま、『杳かなる』という映画が全国で公開されています。
映画『杳かなる』予告篇
https://harukanaru.com/theater
この情報によりご覧頂いた皆様に、少しでも筋萎縮性側索硬化症に対する理解が進むことを期待いたします。


