障害者優先調達を活用したDXによる障害者就労の推進と困難を抱える方々の就労支援について懇談:永田町
5日午後、厚労省の予算概要に関する懇談に引き続き、原田大二郎事務所にて、日本財団 公益事業部 シニアオフィサー 竹村利道氏と懇談しました。
原田大二郎参議院議員が出席し、山本博司氏(前参議院議員)、元厚労省の障害者雇用課長・福岡労働局長を歴任した小野寺徳子氏と共に、輝HIKARIの金子訓隆代表理事も同席しました。

竹村シニアオフィサーからは、国立国会図書館などの中央省庁や福岡県など各自治体のDX(デジタル化)を障がい者施設で進めている枠組みを全国でさらに進めるために議論。
日本財団は、国立国会図書館の蔵書をデジタル化する事業を受注して、2024年度は障害者施設8か所(福岡県・熊本県等)に委託、2025年度は13か所の施設が参加の予定です。
約7億円を超える規模の障害者優先調達となり、一般企業も担う専門性の高い仕事で障害者の賃金向上も大きくはかられる画期的な取り組みです。
また福岡県においてもDXの取組みを日本財団が対応。その下で障がい者就労支援ホームでは障害のある人が撮影用のスキャナーを備えた暗室に入り、本を開いてガラス版で挟み、足元にあるスイッチでシャッターを押す。ゆがみ、ほこり等ノ映り込みがないかを確認して撮影する。隣室では撮影された画像のチェックが丁寧に行われて納品をする体勢を整えています。
先日は、国立国会図書館のデジタル化の状況と障害者優先調達(デジタル化)の取組み(国立国会図書館)について内閣府・厚労省から伺いました。
約4620万点の蔵書がある国立国会図書館は、デジタル化を今後加速させる予定ですし、国立公文書書館など他の国の施設もDX化を進めています。
優先調達を活用し、全国の障害福祉施設でデジタル化推進のための、DX人材育成・支援、行政と連携など進めるべき課題も見えています。
またもう一つのテーマである困難を抱える多様な人々の就労支援についても意見交換しました。
ひきこもり、矯正施設退所者、難病患者など困難を抱える人たちは大勢いますが、就労について制度のはざまになっています。
日本財団ではこうした方々の調査・研究を通じて、ダイバシティ就労の支援を国で進める必要性を訴えてこられました。
障がい者や困難を抱える方々の就労という大事なテーマについて意義ある前向きな話し合いができました。
なお、竹村シニアオフィサーらとの懇談内容は以下の通りです。(若干、数字に違いがあるかもしれません)
障害者就労の新たな地平:DX化と優先調達が切り拓く「月額工賃12万円」への挑戦
日本財団が主導し、政治・行政を巻き込みながら、障害者優先調達推進法を最大限に活用して、障害者の就労機会と所得を劇的に向上させようという壮大な構想。
前参議院議員の山本博司氏、前厚生労働省障害者雇用対策課長の小野寺徳子氏、特定非営利活動法人輝HIKARIの金子訓隆氏、そして日本財団の竹村氏らが交わした議論からは、従来の福祉の枠組みを根底から覆す可能性を秘めた、具体的かつ戦略的な未来図が浮かび上がってくる。その核心は、国立国会図書館などに眠る膨大な紙媒体資料のDX(デジタル・トランスフォーメーション)化を、障害者の新たな仕事として創出することにある。
1.突破口となった国立国会図書館事業と「優先調達」の真価
この取り組みの原点であり、最大の成功事例となっているのが、国立国会図書館(NDL)の蔵書デジタル化事業である。この巨大プロジェクトを障害者の仕事として確保する上で、法的根拠となったのが、山本博司氏らが議員立法で成立させた「障害者優先調達推進法」だ。この法律は、国や地方自治体が物品やサービスを調達する際に、障害者就労施設などに優先的に発注するよう努めることを定めている。
■障壁の打破と巨大市場の開拓
しかし、当初はこの法律にも大きな壁が立ちはだかっていた。WTO(世界貿易機関)の政府調達協定に基づく国際ルールにより、一定額(10万SDR、当時約1500万円)以上の案件は国際競争入札にかける必要があり、優先調達の対象外とされていたのだ。国立国会図書館側もこのルールを盾に、「1500万円以上は出せない。それ以上は一般競争入札に参加してほしい」との姿勢を崩さなかった。一般競争入札となれば、価格競争力や実績で勝る凸版印刷などの大手企業に太刀打ちできないことは明らかだった。
この膠着状態を打破したのが、政治的な働きかけだった。この尽力により、ついに政令が改正され、この上限額が撤廃されたのである。この規制緩和が決定的な転換点となった。日本財団はこの機を逃さず、国立国会図書館から総額6億円という、障害者就労施設への発注としては前代未聞の規模の業務を受注することに成功したのだ。
■「仕事ありき」の支援モデルへの転換
日本財団はこの6億円の事業を全国53ヶ所の障害者就労施設に配分。しかし、単に仕事を割り振るだけでは、このプロジェクトは成功し得なかった。国立国会図書館が求める品質水準でデジタル化業務を遂行するには、高性能なスキャナーやサーバーなど、1拠点あたり約1億2000万円にも上る大規模な設備投資が不可欠だったからだ。
ここで日本財団の真骨頂が発揮される。同財団が持つ潤沢な資金力を活かし、この初期投資を100%補助する形でハード面の環境整備を全面的にバックアップしたのである。竹村氏はこれを「日本財団が得意なのは、財源で整備をしていくこと。ハード整備にぜひ我々を使っていただきたい」と語る。
これは、従来の障害者福祉における補助金のあり方を根本から見直すものでもあった。これまで日本財団も、工賃向上を目的として、パン屋のオーブン購入などに1000万円、2000万円といった補助を行ってきた。しかし、竹村氏が「言葉を選ばずに言えば『売れないパン』のオーブンを買ってください、という補助をきっぱり止めた」と語るように、製品やサービスに市場競争力がなければ、いくら設備を支援しても持続的な成果には繋がらないという厳しい現実に直面してきた。
今回の国立国会図書館事業は、その反省に基づき、「まず確実に収益が見込める大きな仕事を取ってくる。その仕事を遂行するために必要な設備を支援する」という、「仕事ありき」「成果直結型」の全く新しい支援モデルを確立した。これにより、障害者の平均工賃を、従来のB型事業所の全国平均である月額2円程度から、この業態を行う施設は、6倍にもなる月額12万円程度へと引き上げるという具体的な目標が現実味を帯びてきた。この水準は、障害基礎年金の支給が停止されることなく、近年の物価高騰にも対応できる、真の「自立生活」を可能にするための重要な指標である。
2.なぜ「スキャニング・IT業務」なのか?その戦略的ロジック
この構想が、従来の軽作業や食品加工といった福祉的就労と一線を画すのは、その対象業務を「スキャニング」を中核とするIT・デジタル分野に特化している点にある。なぜこの分野が選ばれたのか。その背景には、緻密な戦略と複数のロジックが存在する。
(1)圧倒的な潜在市場規模
まず、デジタル化が必要な公的文書の量は膨大だ。国立国会図書館だけでも、年間40億円規模のデジタル化予算が見込まれ、政府は次年度当初予算で同程度の年間予算を確保し、向こう5年間で210億円規模のプロジェクトになる方向で調整が進んでいる。
しかし、これは氷山の一角に過ぎない。議論の中では、国立公文書館や最高裁判所の判例記録といった、極めて高いセキュリティが求められる文書群もターゲットとして挙げられている。さらに、各中央省庁や地方自治体が保有する行政文書(例:児童相談所の記録、歴史公文書など)も加えると、その市場規模は計り知れない。事実、この取り組みに触発され、福岡県が年間7100万円、青森県が5000万円、東京都江戸川区が8000万円~1億円規模の行政文書デジタル化を障害者就労施設へ発注する動きが既に始まっている。この枯渇することのない膨大な仕事量が、事業の持続可能性を担保しているのだ。
(2)障害者の特性との高い親和性
次に、デジタル業務は、障害のある人々の特性や意欲と非常に高い親和性を持つ点が挙げられる。特に精神障害や発達障害のある人の中には、対人コミュニケーションは苦手でも、PCに向かって黙々と作業することに高い集中力を発揮したり、デジタル技術に強い関心を持ったりする人が少なくない。
小野寺氏が指摘するように、「デジタル系の仕事がやりたかった人はすごくいる」のが現実だ。新潟の事例では、デジタル系の就労支援施設に問い合わせが何百件も殺到し、引きこもっていた若者が社会復帰のきっかけを掴むなど、これまで福祉的就労の選択肢になかった層のニーズを掘り起こしている。彼らにとって、この仕事は単なる収入源ではなく、自己肯定感を高め、社会と繋がるための重要なツールとなり得る。
(3)福祉現場の「ジェネレーションギャップ」の克服
一方で、福祉現場には根強い課題も存在する。多くの福祉施設の職員は福祉の専門家であっても、ITやビジネスの専門家ではない。そのため、IT・デジタル系の業務に対して「難しそうだ」「自分たちには分からない」という苦手意識や、「障害者には向いていない」という無意識の思い込み(ジェネレーションギャップ)が存在する。これが、新たな就労機会の導入を妨げる大きな障壁となってきた。
この課題を克服するため、日本財団がハード整備から業務のマネジメントまでを主導する現在のスキームは極めて有効だ。施設側は、最もハードルの高い設備投資や営業活動、技術的なノウハウの導入といった負担から解放され、利用者への直接的な支援に集中できる。これにより、福祉現場の職員が抱える「伝家の宝刀」(=障害者には向いてないから、という言い訳)を封じ、デジタル分野への挑戦を後押しする。
(4)高付加価値による工賃向上への直結
そして最も重要な点が、デジタル化業務が持つ高付加価値性である。従来の箱詰めやシール貼りといった内職的な軽作業は、誰にでもできるがゆえに単価が極めて低く、どれだけ長時間働いても工賃向上には限界があった。しかし、公的文書のスキャニング業務は、品質管理やセキュリティ担保が求められる専門的な仕事であり、それに伴って作業単価も高く設定される。安定した大規模な受注と高い業務単価が組み合わさることで、初めて「月額12万円」という目標が現実的なものとなるのだ。
3.未来への展望:BPOナショナルセンターとインクルーシブ雇用
国立国会図書館事業の成功は、ゴールではなく、あくまで壮大な構想の第一歩に過ぎない。竹村氏らが描く未来図は、さらに二つの大きなステップへと繋がっている。
構想1:BPOナショナルセンターの設立
第一の構想は、「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)ナショナルセンター」の設立である。これは、デジタル化業務の受発注に特化した、全国規模の司令塔機能を持つ専門機関を創設しようというものだ。
現状、全国には111ヶ所の「共同受注窓口」が存在するが、その多くが機能不全に陥っている。国から年間10億円近い予算が投じられているにもかかわらず、例えば「2500万円の運営コストをかけて年間の受注高は800万円にも満たない」といった非効率な実態が指摘されている。その原因は、職員が入札や応札といったビジネス実務に不慣れなことにある。
BPOナショナルセンターは、こうした既存の窓口とは一線を画し、各省庁や全国の自治体からDX関連の大型案件をプロとして一括受注し、それを全国のデジタルセンター(作業拠点)へと適切に再配分する「プロデューサー」の役割を担う。当初の立ち上げ3年間は国の支援を求めつつ、将来的には受注額の10%程度を運営費とすることで自立を目指す。これにより、アナログ業務は既存の共同受注窓口、デジタル業務はBPOナショナルセンターという棲み分けを行い、より専門的で効率的な受発注システムを構築する狙いだ。
構想2:「ワークダイバーシティ」とインクルーシブ雇用への進化
第二の、そしてより本質的な構想が、支援の対象を障害者に限定せず、多様な就労困難者へと広げる「ワークダイバーシティ」の実現である。
現在の障害者雇用制度では、福祉サービスを受けるために、本来は必要のない人まで心療内科にかかり、「適応障害」などの診断名を得て手帳を取得せざるを得ないという矛盾を抱えている。
この構想は、こうした「レッテル貼り」から脱却し、障害者に加え、引きこもり、がんサバイバー、刑務所出所者など、働く上で困難を抱える全ての人々を包摂する新たな支援の仕組みを目指す。その出口戦略として、諸外国で導入されている「インクルーシブ雇用率」という考え方が提示された。これは、法定雇用率のような義務的なものではなく、多様な人材を雇用する企業に対して税制優遇などのインセンティブを与える理念的な目標として位置づけられる。
この壮大なビジョンを実現するため、自民党の野田聖子氏や木村弥生氏が中心となり、公明党なども巻き込んだ超党派の議員連盟の設立が計画されており、2025年11月12日にはその第一回会合が予定されている。これは、障害者福祉という枠を超え、日本の社会全体の働き方、そして「共生社会」のあり方を問い直す大きなうねりとなる可能性がある。
議論の終盤、山本博司氏らは、まずは一足飛びに議連や大きなスキームを目指すのではなく、総務省管轄の公文書館のデジタル化状況をヒアリングするなど、着実な実績を積み重ねていくことの重要性を確認した。一つの成功事例が次の扉を開き、それがまた新たな展開を生む。
日本財団の資金力と事業推進力、政治家たちの政策実現に向けた情熱、そして福祉現場の実践。これらが三位一体となって駆動するこのプロジェクトは、単なる障害者の工賃向上策ではない。DXという時代の要請を的確に捉え、これまで「支援される側」と見なされてきた人々の潜在能力を最大限に引き出し、彼らを社会の重要な担い手へと変えていく、日本の福祉政策における一大転換点となる可能性を秘めている。砂漠に水を撒くような従来の福祉から、持続可能な生態系を育む「森」を作る福祉へ。その挑戦は、今まさに始まったばかりだ。
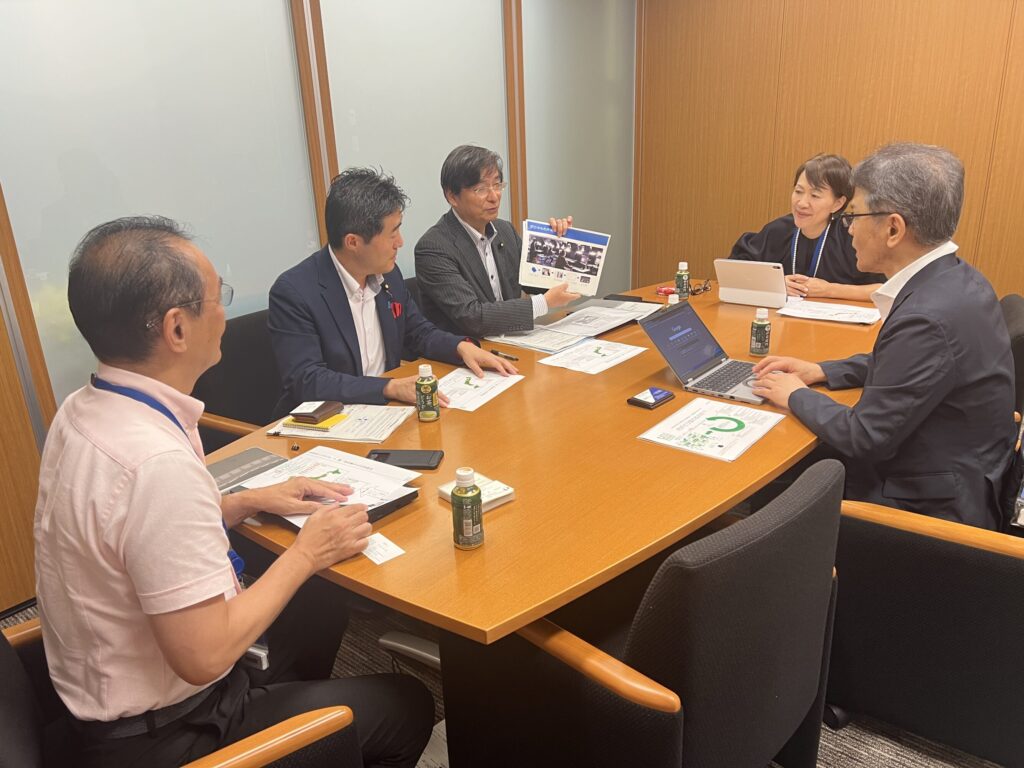

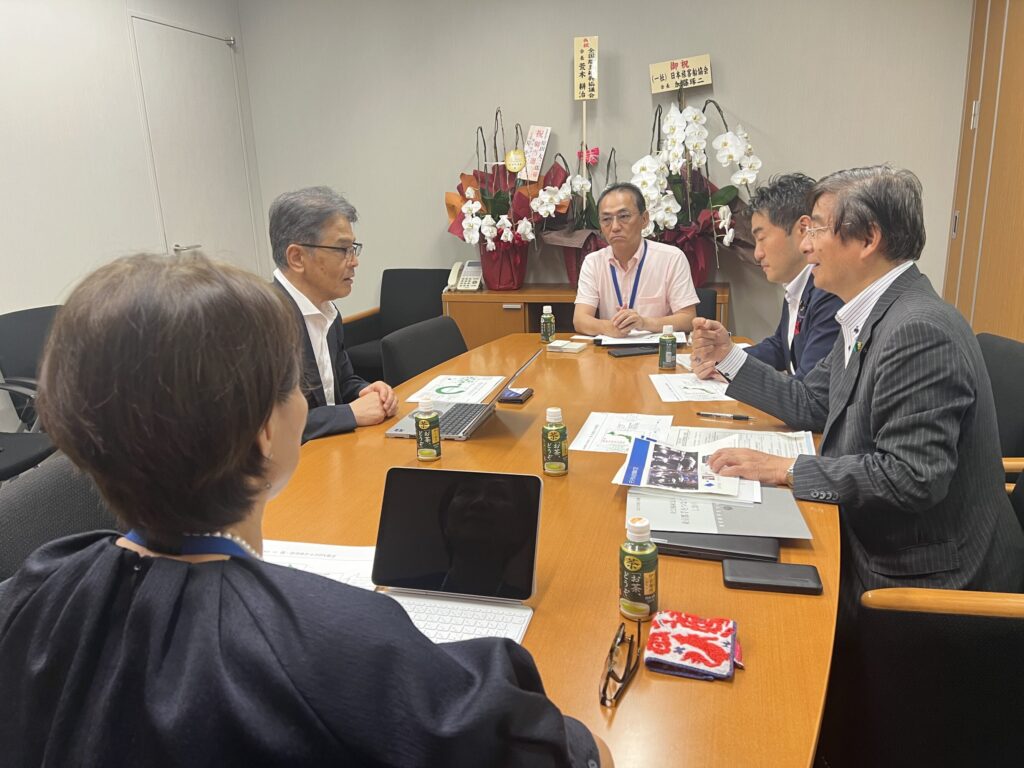
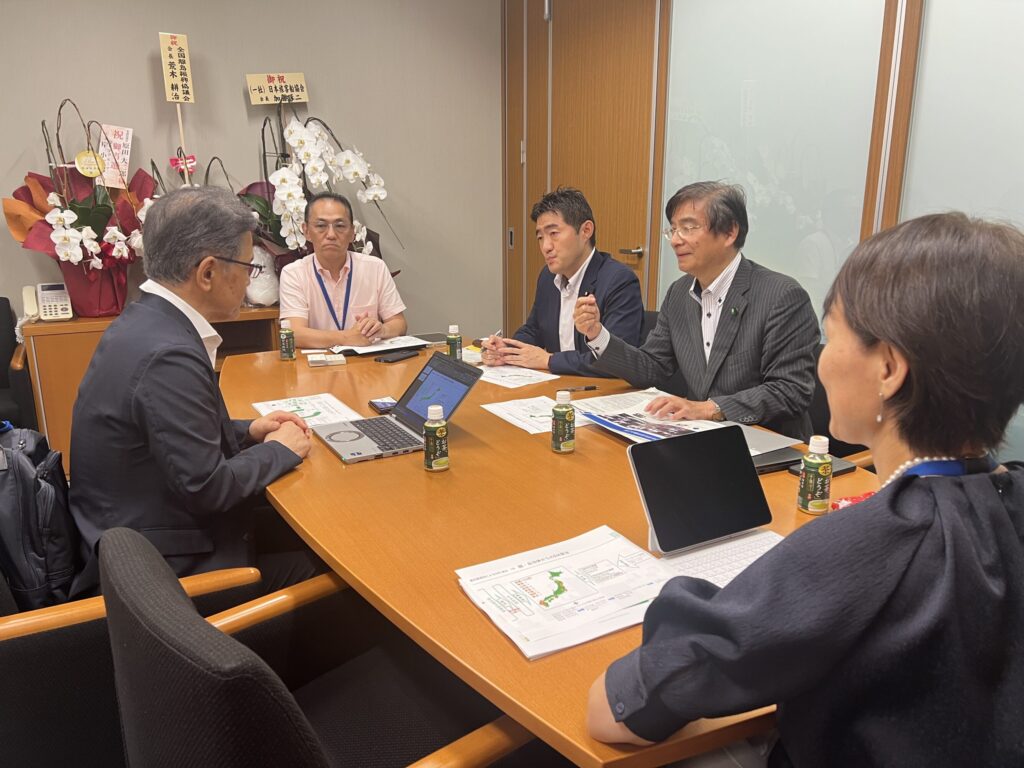




“障害者優先調達を活用したDXによる障害者就労の推進と困難を抱える方々の就労支援について懇談:永田町” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。